ドビュッシー 「海」
私が、ドビュッシーに開眼したのは、勤務先の吹奏楽部と一緒に武蔵野音大まで遠征した際、天理高校の演奏で、吹奏楽編曲の「海」第3楽章を聴いた時である。彼らはたった50人で、総木造りのホールで大変ダイナミックで切れのある演奏をした。それを聴いて、ドビュッシーが現代音楽の最初の作曲家である、ということを初めて実感できたのである。(それまではカラヤンやアンセルメでしか聴いたことがなかった。)
その2年後、私の高校の吹奏楽部も同じ「海」第3楽章を演奏することになった。それを機会にこの曲のCDを買い集め勉強し、同部の練習で指揮もした。いや、実に面白い曲である。こういう曲は、聴くより演奏するほうが面白い。
で、その勉強の過程で、次のようなことに初めて気が付いた。
「海」第3楽章、スコアの練習番号59の4〜11小節(=練習番号60の直前8小節)。ここは、弦と木管だけで緊張感あふれるユニゾンの第2主題(?)を奏することになっている。
ところが、かなり多くのレコードにおいて、ここにトランペットが「パッパーパパパー」と合いの手を入れてくるのである。そんなのはスコアにないのだが、アンセルメあたりが始めたことだという。
このトランペットの合いの手が入ることによって、そこでの主役の座がトランペットに移り、弦と木管は緊張感もなくただ伴奏をつけているだけになってしまう。ハッキリ言って改悪としかいいようがないのだが、名のある指揮者がかなりこれを採用しているので、ますます困ったことになっている。
ところが、この問題について、99年9月、この曲をこよなく愛する「熊蔵さん」からメールをいただき、次のような指摘を受けた。→熊蔵さんの「海」の楽譜についてのページ
あの金管の合いの手フレーズを作曲したのはドビュッシー自身で、この曲の1905年初版には存在している。しかしこの曲はその後1909年・1938年の2度にわたって改訂を受けており、その過程で問題のフレーズは削除された。そのフレーズを現行の楽譜の上に復活させたのは確かにアンセルメである。
これは私にとっては大変驚くべき情報であった。私が所有しているこの曲のスコアは、全音楽譜出版社のものであるが、このスコアにはどうも「出自不明」である上に、版の問題が存在することについての解説が全くないのである。
しかし、私はデュオ・クロムランクによる「1台4手によるピアノ連弾版」のCD(claves)を所有しており、その解説をよく読み、その演奏を注意深く聴いておけば、間違った情報をこのページに記述することはなかったのであった。なぜなら、この作曲家自身による「1台4手ピアノ連弾版」は「オーケストラ初版」のもととなったものであり、ここには後に例のトランペット・パッセージがちゃんと聞き取れるのである。
ドビュッシーは、1905年3月5日に「1台4手によるピアノ連弾版」を完成させた。「オーケストラ初版」(Durand&Fils)の総譜はその年10月のコンセール・ラムルーによる初演直前になってやっと書き上げられたという。
その後、1909年に「オーケストラ第2版」(Durand&Fils)、1908〜10年頃に「2台4手によるピアノ連弾版」が成立する。これらがドビュッシー自身によるこの曲の改訂の最後のものである。おそらくこの段階で、例のトランペット・パッセージは削除されていた、と考えられる。(また、このオーケストラ第2版が、全音楽譜出版社のスコアのもととなっていると推測される。)
ドビュッシーは1918年に死去するが、その20年後(!)、1938年に「オーケストラ第3版」(Durand&Cie)が出版される。これは、作曲家死後のことであり、正統性のあるものなのか疑問も残るが、しかしこれが現在の演奏の基本スコアとなっている。
1971年、PETERS社から、自筆譜・1909年版・1938年版をマックス・ポンマーが校訂したスコアが出版される。これは日本では音楽之友社から1992年に出版されている。また1983年にはドーバー社からも新しい校訂版が出版されており、PETERS社とは違った処理をしているところもあるという。
以下に各版の特徴をまとめておく。ポイントはいずれも第3楽章の次の3点に絞る。(ただし、「1909年第2版」の楽譜は、熊蔵さん及び私のいずれも未確認である。)
- 1. 練習番号60の前8小節のトランペット・パッセージの有無
-
上記の通り、初版には存在したが、おそらく1909年頃の改訂では削除されていた、と考えられる(未確認)。少なくとも、1938年以後の現行のどのオーケストラ版印刷譜にも存在しないことは確かである。
しかし、アンセルメが1938年版のスコアの上にこのパッセージを復活・演奏して以後、多くの著名な指揮者がこのパッセージを演奏している。 - 2. 練習番号62からのコルネットの音形の違い
-
1909年オーケストラ第2版、および全音楽譜出版社のスコアには、「2連符・3連符・2連符・3連符」という小節が4小節繰り返されている。1905年「1台4手ピアノ連弾譜」も同様であり、デュオ・クロムランクらよるCDでも確認できる。オーケストラ録音でこのように演奏しているのは、モントゥー指揮ボストン響のモノラル盤と、ミュンシュ指揮のトスカニーニ追悼コンサート盤だけである。
しかし、1938年第3版以後の楽譜は全て、4小節のうち最初の2小節は「2連符・3連符・二分音符」となっている。そして上記2盤を除く下にあげた全てのオーケストラ盤CDもそのように演奏している。
ところが、ここで不思議なことが1つある。それは、1938年版の出版より前の1935年のトスカニーニ指揮BBC響のライヴ盤も「2連符・3連符・二分音符」となっていることである。(トスカニーニが新しい出版譜の情報を事前に得ていたのか? それとも1938年版自体が昔のドビュッシーの指示により1909年版の誤りを訂正したものということなのか?) - 3. 練習番号63からコルネットの3連符音形の有無
-
全音楽譜出版社のものには、この「コルネット3連符音形」が存在する。1905年「1台4手ピアノ連弾譜」によるデュオ・クロムランクの演奏にもそれに相当する音形が確かに聞き取れる。
全音楽譜出版社のスコアが1909年第2版に由来すると仮定すれば、それにも「コルネット3連符音形」が存在したと考えられる。熊蔵さんによれば同じ頃の作曲家自身による「2台4手ピアノ連弾譜」には、それに相当する音符があるという。
同じく熊蔵さんからの情報によれば、その後は、- 1938年、第3版・・・「コルネット3連符音形」無し
- 1971年、PETERS社・・・「コルネット3連符音形」を復活
- 1983年、ドーバー社・・・「コルネット3連符音形」無し
となるらしい。
なお、1935年のトスカニーニBBCライヴではこの「コルネット3連符音形」は演奏されていない。このことからも、1938年第3版は、それ以前からの情報の整理である可能性が高いと考えられる。
しかし、下にあげたCDのうち、ライナー、モントゥー、ミュンシュBSO、セル(ケルンでのライヴ)、ミトロプーロスといった50〜60年代にアメリカで活動していた指揮者が「コルネット3連符音形」を演奏しているのは興味深い。一方ブーレーズはニューフィルハーモニアとのSONY旧録音では演奏していないが、DGへのデジタル新録音では演奏させている。
以上、いろいろな版の経緯について概観してみた。
私の所有する「全音楽譜出版社のスコア」は、「練習番号60の前8小節のトランペット・パッセージ」が削除されていることを除けば、1905年の「1台4手ピアノ連弾譜」の持つ「原型」をとどめていることから、1905年初版と1938年第3版の間の形態、すなわち1909年第2版に由来するものである、と私は考えている。
つまり、「トランペット・パッセージ」はドビュッシー自身によって削除された、と私は考えており、よって、アンセルメによるトランペット・パッセージの復活は「改悪」である、という考えには変わりがない。
「練習番号63からコルネットの3連符音形」については、私は熊蔵さんに指摘されるまで、こんな問題があるとは気が付かなかった。しかし、これが入っている録音を聴くと、これは「あったほうが絶対に華々しい」と思う。いかにも20世紀初頭の音楽といった趣がある。
ということは、上記2点を満たす唯一の録音、すなわちブーレーズのDG新録音が、もっとも曲本来の姿を表している演奏ということにならざるを得ない。
以下のディスクのうち特に付記していないものは「トランペット・パッセージ無し」である。
モノラル録音
だいたい、何を好きこのんで印象派をモノラルで聴かにゃならんの、という人も多いだろう。しかし、トスカニーニ、モントゥー、サバタ、カンテルリの演奏は是非聴いてほしい。そうすれば、ステレオ録音の中で、輪郭のボケた演奏をして、それが「印象派」だ、と聴衆を錯覚させてきた多くの指揮者を、逆に無能だと思うようになるだろう。
- アルトゥーロ・トスカニーニ指揮BBC交響楽団
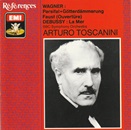
-
EMI。1935年6月12日、クイーンズ・ホールでのライヴ録音。トスカニーニのうなり声付き。
上記解説のように、1938年第3版出版前の演奏であるにもかかわらず、第3版の特徴が聴かれる。
すなわちトスカニーニの演奏は「トランペット・パーセッジ無し」「2連符・3連符・二分音符」「コルネット3連符なし」であり、下のNBC盤も同じである。
当CDのカップリングはヴァーグナーの「パルジファル」前奏曲&聖金曜日、「ジークフリートの死と葬送行進曲」、「ファウスト」序曲 でいずれも35年6月ライヴ。 - アルトゥーロ・トスカニーニ指揮NBC交響楽団

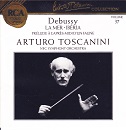
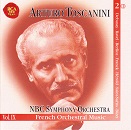
-
RCA。1950年6月1日、8Hスタジオでの録音。
- ピエール・モントゥー指揮ボストン交響楽団

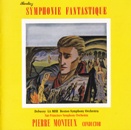
-
RCA。1954年7月19日録音。
モントゥー唯一の同曲録音でタングルウッド音楽祭での実演直後に録音された。
この録音は実におもしろい。上の問題点3つが全て出揃っている。
まず「トランペット・パッセージ付き」である。
珍しいのは第2点の練習番号62からのコルネットが「2連符・3連符・2連符・3連符」で4小節繰り返されている。これは上に書いたとおり第2版の特徴である。
最後の練習番号63からコルネットの3連符音形がこれほどよく聞こえる録音も他にない。
なお、このCDのメインはサンフランシスコ響との「幻想」である。24bit-96kHzリマスター国内盤。 - シャルル・ミュンシュ指揮シンフォニー・オヴ・ジ・エア
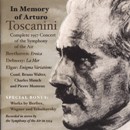
-
M&A CD-1201。1957年2月3日、カーネギー・ホールでのトスカニーニ追悼コンサートのライヴ2枚組。
ワルターの「英雄」のあとに演奏された。さらにそのあとにモントゥー指揮の「エニグマ変奏曲」。
トランペット・パッセージ付き、コルネット3連符付き、そして練習番号62からのコルネットが「2連符・3連符・2連符・3連符」で4小節繰り返されている。つまり上記モントゥー盤と同じ特徴である。ということはトスカニーニと正反対ということでもある。
(下のボストン響との録音では練習番号62からが「2連符・3連符・二分音符」になっている。) - ヴィットリオ・デ・サバタ指揮聖チェチリア音楽院管弦楽団

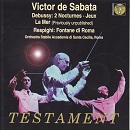
-
TESTAMENT SBT 1108。1948年録音。
「トランペット・パッセージ付き」だ・・・ん??いや違う!!
何とその追加パッセージをホルンでやらせているではないか!
チェリビダッケの最晩年と同じだ! これには驚いた。
というわけで、楽譜通りではないのだが、演奏全体としては、現代音楽としてのドビュッシーをきちんと表現している。熱いラテンの血は、トスカニーニに勝るとも劣らない。よって名盤指定。 - ディミトリ・ミトロプーロス指揮ニューヨーク・フィル
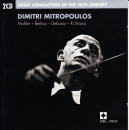
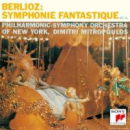
-
SONY原盤。1950年11月27日、30th Street Studioで録音。
GREAT CONDUCTORS OF THE CENTURYシリーズ(EMI IMG)2枚組。
トランペット合いの手あり。コルネット3連符あり。音質・演奏とも良い。
2012年に国内盤SICC-1600(メインはステレオ録音の幻想交響曲)でも出た。 - ジョージ・セル指揮ケルン放送交響楽団
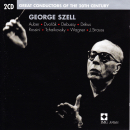
-
GREAT CONDUCTORS OF THE CENTURYシリーズ(EMI IMG)2枚組。
1962年11月16日、放送用ライヴ録音。
トランペット合いの手なし。コルネット3連符あり。
翌年のクリーヴランド管とのSONY盤は持っていない。 - グィド・カンテルリ指揮フィルハーモニア

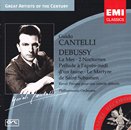
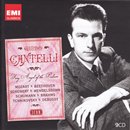
-
EMI。ART処理。1954年録音。なんと瑞々しい。
- デジレ=エミール・アンゲルブレシュト指揮フランス国立放送管弦楽団

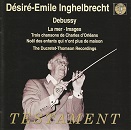
-
TESTAMENT SBT 1213。1954年録音。
彼の特徴は下のステレオ盤に書いた通り。 - ハンス・ロスバウト指揮南西ドイツ放送交響楽団

-
SWR Classics。1958年1月16日、ハンス・ロスバウト・スタジオでの録音。
“現代音楽工房”での素晴らしい録音である。トランペット合いの手無し。
ステレオ録音
- エルネスト・アンセルメ指揮スイス・ロマンド管弦楽団
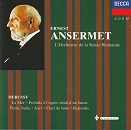
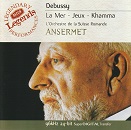
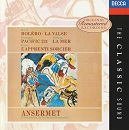
-
DECCA。2種類の録音とも「トランペット・パッセージ付き」。
アンセルメはこのパッセージを復活させた張本人である。
写真左から、
「433 711-2(※)」
「470 255-2 (1957年10月録音)」
「448 576-2 DECCA LEGENDS(1964年12月録音)」。
※は64年録音と表記されているが、演奏時間を比較するとDECCA LEGENDS盤と同じ57年録音である。この2つが速めのテンポで、64年盤はやや遅い。 - ポール・パレー指揮デトロイト交響楽団
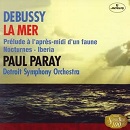
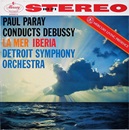
-
マーキュリー。UCCP-7077。1955年12月録音。
パレーは作曲家だけあって、やはりトランペット・パッセージは無し。
「牧神」「イベリア」「夜想曲」とカップリング。
右はオリジナルLP(「イベリア」と)。 - ミヒャエル・ギーレン指揮シンシナティ交響楽団

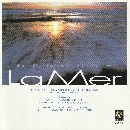
-
VOX。1984年録音。名演である。
すべてが明晰に生き生きと鳴り響くさま(最後のトランペットの上昇音型!)はブーレーズ旧盤をも凌ぐ。
スクロヴァチェフスキ指揮の「ダフニスとクロエ」第1・2組曲とカップリング。 - シルヴァン・カンブルラン指揮南西ドイツ放送交響楽団
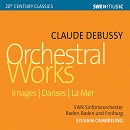
-
SWR。2004年録音。トランペット・パッセージ無し。
比較的遅めのテンポで表情付けしている。 - フランソワ=グザヴィエ・ロト指揮ル・シエクル
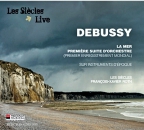
-
Actes Sud。2012年4月13日、ローマ、聖チェチーリア音楽院でのライヴ録音。
楽器は1905年初演当時のフランスのものを再現し、当然ガット弦である。管楽器も現代とは違う。
カップリングは長く失われていた管弦楽組曲第1番の世界初演ライヴ録音である。 - フランソワ=グザヴィエ・ロト指揮ロンドン交響楽団
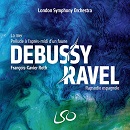
-
LSO。SACD-hybrid。2018年、バービカンホールでのライヴ録音。
トランペット・パッセージ無し。 - ジョス・ファン・インマゼール指揮アニマ・エテルナ
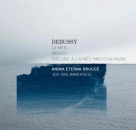
-
ZIGZAG。2012年2月9日、ブリュージュでのライヴ録音。
トランペット・パッセージ無し。 - クラウディオ・アバド指揮ルツェルン祝祭管弦楽団
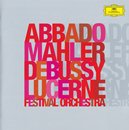

-
DG。2003年8月14日、Kultur und Kongresszentrumにおける音楽祭初日のライヴ録音。 第3楽章8:02。最後はライヴとはいうもののアバドにしては珍しくらしくだいぶ煽っている。終演後、ちょっと間をおいてブラボーと大喝采入り。
驚いたことにトランペットの合いの手がしっかり入っている(初期稿優先ということなのだろうか?)。一方、最後にはコルネット3連符音型も華々しく鳴っている。この組み合わせは、ライナーCSO、ミュンシュBSOと同じである。
音楽祭締めのマーラー「復活」とカップリング2枚組。なお、この祝祭管は、2003年にアバドを芸術監督に迎えたのを機に新しく改組されたものである。(詳しくは「復活」のページで。)EuroArtから出た輸入盤DVDも入手。こちらは同日演奏の「聖セバスティアンの殉教」組曲とのカップリングである。
完全にガンを克服したアバドの元気な指揮ぶりを見ることができる。
また、「ルツェルン祝祭管の歴史」というドキュメンタリーも入っている。 - デジレ=エミール・アンゲルブレシュト指揮フランス国立放送管弦楽団

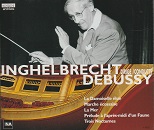
-
AUDIVIS。V 4857。1962年1月23日ライヴ録音。
以前ディスク・モンテーニュから発売されていたアンゲルブレシュト指揮のドビュッシー作品のライヴ録音の復活6枚組セット。単品ではV 4856(写真)。
トランペット・パッセージ無しの部分で、もの凄くテンポを溜めている。「フランスの香り」という点でブーレーズ盤にまさる。 - マヌエル・ロザンタール指揮パリ国立歌劇場管弦楽団

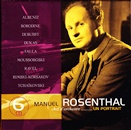
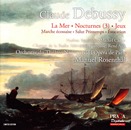
-
ACCORD。1957〜59年録音。
ドビュッシーの他、ラヴェルの管弦楽曲集など6枚組セット(写真左)。
2013年、PRAGAレーベルからSACD Hybrid盤が出た(写真右)。しかしこれはmercariで売却した。 - ジャン・マルティノン指揮フランス国立放送管弦楽団

-
EMI。1973年録音。彼の全集はスタンダード。
- ピエール・ブーレーズ指揮ニューフィルハーモニア

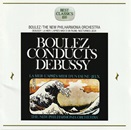
-
SONY。1966年録音。メリハリのきいた最高の名演。
- ピエール・ブーレーズ指揮クリーヴランド管弦楽団

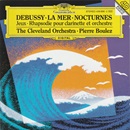
-
DG。1991年新録音。演奏全体として丸くなっており、旧盤のほうが演奏としては好きだ。
しかしこちらは、「トランペット・パッセージ無し」で、かつ練習番号63の「コルネット3連符音形」がある、という模範的演奏なので「決定盤」。 - シャルル・ミュンシュ指揮ボストン交響楽団
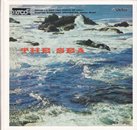
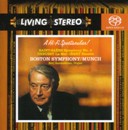
-
RCA。1956年録音。
「トランペット・パッセージ付き」。練習番号63の「コルネット3連符音形」有り。
LIVING STEREO盤の他、2000年にXRCDで発売されたものも入手(左)。
2009年、LIVING STEREOのSACD Hybridも入手(右、オルガン交響曲とカップリング)。XRCDは売却することにした。 - シャルル・ミュンシュ指揮フランス国立放送管弦楽団

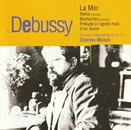
-
コンサートホール原盤。fnac。輸入盤。1968年録音。
69年ACCディスク大賞および70年ADFディスク大賞を受賞。名演だ!
こちらは「トランペット・パッセージ無し」(コルネット3連符も無し)。
この現象がよく理解できない。何で、フランスに戻っての新録音はこうなのか。 - シャルル・ミュンシュ指揮パリ管弦楽団
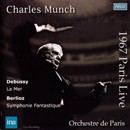
-
Altus。1967年11月14日、シャンゼリゼ劇場でのパリ管発足演奏会ライヴ録音。
やはり上のフランス国立放送管同様「トランペット・パッセージ無し」(コルネット3連符も無し)。
記念すべきライヴということでテンポの変化はもの凄い。メイン曲の「幻想交響曲」とカップリング。 - フリッツ・ライナー指揮シカゴ交響楽団
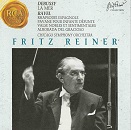
-
RCA。1960年録音。
「トランペット・パッセージ付き」。練習番号63の「コルネット3連符音形」有り。
ミュンシュBSOも同じなので、これはRCAが用意した楽譜がそうなっていたのだろうか? - ユージン・オーマンディ指揮フィラデルフィア管弦楽団
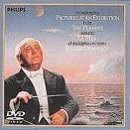
-
PHILIPS(UNITEL)。DVD。「トランペット・パッセージ無し」(コルネット3連符も無し)。
1977年6月24-26日、フィラデルフィア、アカデミー・オブ・ミュージックでのライヴ収録。
同日演奏のホルスト「惑星」、および翌78年収録の「展覧会の絵」がカップリングされている。
フィラデルフィア管の本拠地だったアカデミー・オブ・ミュージックは、旧オペラ劇場だったようだが、音響はあまり良くない。オーマンディといえばこのオケとのコンビで、華麗なフィラデルフィア・サウンドを作ったとされている。しかしオーマンディ自身はその言葉を日本で初めて聞いたとインタビューか何かに答えていたようだ。このコンビは基本的レコード録音をタウン・ホールという建物の舞踏会場で行っていた。このDVDに聴く音は華麗でも何でもない。むしろ質実剛健と聞こえる。加えてオーマンディの指揮がまた、模範的とも言うべき最小限の棒の動きで、同郷(ハンガリー)のフリッツ・ライナーのようである。どうも日本ではライナーやセルは高評価でもオーマンディは通俗的で格下であると考えられてきた。
しかしこのDVDにはいわゆる通俗的名曲が収録されているが、オーマンディの指揮ぶりは全く正統的なものである。 - ロリン・マゼール指揮ウィーン・フィル
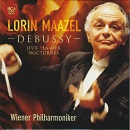
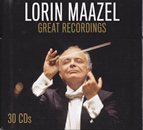
-
RCA。1999年1月、ムジークフェラインでの録音。
「トランペット・パッセージ無し」(コルネット3連符も無し)。 - カルロ・マリア・ジュリーニ指揮フィルハーモニア

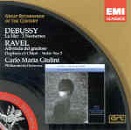
-
EMI。1962年録音。GREAT RECORDINGS OF THE CENTURYシリーズART処理輸入盤。
きびきびした名演である。下のコンセルトヘボウとの新録音とはえらく違う。 - カルロ・マリア・ジュリーニ指揮ロサンゼルス・フィル
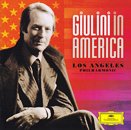
-
DG。1979年録音。
2011年、LAPO録音集6枚組で初入手。LAPOのパリッとした音がこの曲に合っている。名演。 - カルロ・マリア・ジュリーニ指揮コンセルトヘボウ

-
ソニー。1994年録音。レコード・アカデミー賞。(私には輪郭のボケた演奏に聞こえるが..)
- ジョン・バルビローリ指揮パリ管弦楽団
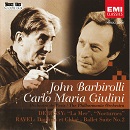
-
EMI。1968年12月録音。
トランペット・パッセージなし。この部分は粘っても良いが、とにかく全編粘りけがありすぎるのが問題だ。 - ハンス・ツェンダー指揮ザールブリュッケン放送交響楽団
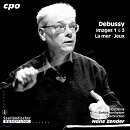
-
cpo。1973年9月11-13日、ザール放送大ホールでの録音。
現代的名演だ。 - シャルル・デュトワ指揮モントリオール交響楽団
-
DECCA。1989年録音。「トランペット・パッセージ付き」なのが残念だ。
DECCAがアンセルメの後継者としてデュトワを使っていることと関係あり、か? - レナード・バーンスタイン指揮聖チェチリア音楽院管弦楽団


-
DG。1989年6月のライヴ録音。
このトランペット無しのパッセージでバーンスタインの「うなり声」を期待してしまうが、録音には入っていない。しかし、指揮する顔が目に浮かぶようだ。
演奏全体としても、正しい意味で「ユニーク」である。静かに沈潜するところのテンポはかなり遅く丁寧にやっている。第3楽章は9分を越えている。 - ダニエル・バレンボイム指揮パリ管弦楽団
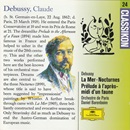
-
DG。輸入廉価盤。1978年録音。
トランペット無し。 - ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮ベルリン・フィル
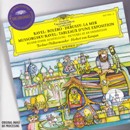


-
DG。1964年録音(左)と1985年録音(中)の2種類のOIBP盤。
EMI。1977年録音(右)のHybrid SACD国内盤。
(他にUNITELの1978年DVDもある。)
いずれも「トランペット・パッセージ付き」である。
旧録音のほうが演奏がキビキビしていて良い。またトランペットがドイツのロータリー式の音色なのがよくわかる。 - セルジュ・チェリビダッケ指揮ミュンヘン・フィル
-
EMIによる正規発売。1992年9月ライヴ録音。異様に遅いテンポで第3楽章は11分以上!
しかも、なんとトランペットではなくホルンで例のパッセージをやっている。 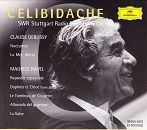 セルジュ・チェリビダッケ指揮シュトゥットガルト放送交響楽団
セルジュ・チェリビダッケ指揮シュトゥットガルト放送交響楽団
-
DG。OIBP化された正規発売盤。1977年2月11日ライヴ録音。
リハーサル風景も収録されている。
テンポが普通であり抵抗がない。(下の海賊盤も)
上のミュンヘン・フィル盤同様、付加パッセージを「ホルン」でやっている。 - セルジュ・チェリビダッケ指揮シュトゥットガルト放送交響楽団
-
ARTISTS。海賊盤である。
これは付加パッセージが「トランペット」である。ということは正規盤よりも古い録音であろう。
ピアノ連弾版
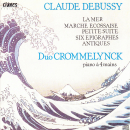 デュオ・クロムランク
デュオ・クロムランク
-
claves。1985年録音。
フランス人のパトリック・クロムランクとその夫人の桑名妙子によるピアノ・デュオ。
「小組曲」「スコットランド風行進曲」「古代のエピグラフ」とのカップリング。作曲家自身による版である。