ショスタコーヴィチの交響曲
全集
- ヴァレリー・ゲルギエフ指揮マリインスキー歌劇場管弦楽団
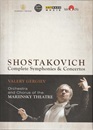
-
ARTHAUS。Blu-ray4枚組。交響曲・協奏曲全集。
2013-14年、パリ、サル・プレイエルでのライヴ収録。
オーケストラは「キーロフ管弦楽団」と同じものである。ソ連崩壊翌年に劇場名が帝政時代と同じマリインスキー劇場となったので、オケ名も本来は上記のように表記すべき所、PHILIPSはずっとキーロフ管弦楽団と表記し続けていただけである。
特典映像:ドキュメンタリー『ドミトリー・ショスタコーヴィチ:いくつもの顔を持つ男』(2015年、ライナー・モーリッツ監督)がついている。しかしこれはmercariで売却した。ゲルギエフが、ウクライナ侵攻を行ったプーチン大統領を支持していることもある。彼は2014年3月のクリミア併合の直前のソチ・オリンピックでも五輪旗を持つ一人だったはず。そんなこともあり、彼のショスタコーヴィチを映像付きで見る気がおこらないのである。
- アンドリス・ネルソンス指揮ボストン交響楽団
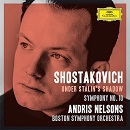
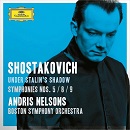
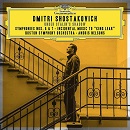
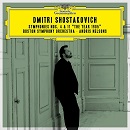
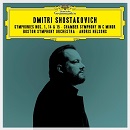

DG。次の6点で全集完成。
479 5059・・第10番(2015.4)
479 5201・・第5番(2015.10)、第8番(2016.3)、第9番(2015.11)
479 5208・・第6番(2017.4-5)、第7番(2017.2)
483 5220・・第4番(2018.3-4)、第11番(2017.9-10)
486 0546・・第1番(2018.11)、第15番(2019.4)、第14番(2018.2)、室内交響曲op.110a(2020.1)
486 4965・・第2番・第12番(2019.11)、第3番(2022.10)、第13番(2023.5)これらDG録音に先んじて、第7番がバーミンガム市響との2011年ライヴでORFEOから発売されていた。
- キリル・コンドラシン指揮モスクワ・フィル

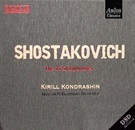
ロシア共和国合唱団、アルトゥール・エイゼン(B,13)
エフゲーニャ・ツォロヴァルニク(S,14)、エフゲニー・ネステレンコ(B,14) -
メロディア。1961〜75年にかけて録音された世界初の全集録音である。
またコンドラシンは第4番(1961.12.30)と第13番(1962.12.18)という2曲の政治的に危険があった曲を初演している。
2004年1月、韓国レーベルAulosがメロディア音源をDSDリマスタリングした全集セットを入手した。カートンBOX入り10枚組で、BOXは磁石でフタが閉まるようになっている。デザインも渋くて良い。ブックレットには英語の他に当然ながらハングル文字の解説も載っている。録音データもきちんと掲載されている。
いかにリマスタリングされたとはいえ、今の録音水準からすると音質の薄さは否めない。しかしもともとこれらの曲は、大オーケストラをフルに鳴らすことを主眼とはしていない。第7番のような曲でも(1枚で収録)決して熱くなりすぎず、効果狙いの演奏の対極に位置するものとなっている。(ソ連体制下では、この曲を脳天気にケバケバしく演奏する気には決してなれなかったであろう。)なお、コンドラシンは亡命後、1980年にバイエルン放送交響楽団と第13番をライヴ録音している(PHILIPS、下記)。
- ムスティスラフ・ロストロポーヴィッチ指揮

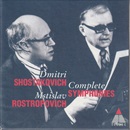
ワシントン・ナショナル交響楽団(1,4-9,11,13)、ロンドン交響楽団(2,3,10,12,15)
モスクワ・アカデミー交響楽団(14)、ガリーナ・ヴィシネフスカヤ(S,14)、マルク・レシェティン(B,14) -
TELDEC。1989〜95年録音。
ただし、第14番だけは、在ソ連時代1973年にメロディアに録音したものを収録している。メロディア盤CDはオケの名を「モスクワ・フィル・ソロイスツ・アンサンブル」としている。第5番は、これより先DGに同じオケと録音しているが、こちらの全集盤のほうが格段に感動的だ。
- ルドルフ・バルシャイ指揮ケルン放送(WDR)交響楽団

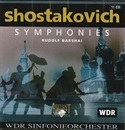
-
BRILLIANT。1992〜98年録音。
ドイツ・レコード批評家賞受賞盤。11枚組で3490円という超廉価盤だが、演奏はロストロ盤以上の名演であると思う。第5番の終楽章でテンポが速すぎないのが気に入った。バルシャイは、1969年10月6日に第14番「死者の歌」を初演した直後、同曲をモスクワ室内管と録音しているが、CD化されているかどうか未確認。
また、彼自身がショスタコーヴィチの弦楽四重奏曲を室内管弦楽団のために編曲した「室内交響曲」を数曲、水戸室内管(SONY)やヨーロッパ室内管(DG)と録音している。
全集ではない、主な指揮者の録音
- エフゲニ・ムラヴィンスキー指揮レニングラード・フィル

-
ショスタコーヴィチと言えばムラヴィンスキーである。
彼は、第5番の初演を1937年11月21日に行って以来、第6番(1939.11.5)、第8番(1943.11.4、ソヴィエト国立交響楽団と)、第9番(1945.11.3)、第10番(1953.12.17)、第12番(1961.10.1)の初演を行っている。また第11番は、1957年10月30日のモスクワにおける初演は指揮しなかったがその直後の11月3日にレニングラード初演を指揮している。
またレニングラード・フィルは、ムラヴィンスキーが就任する前にも、第1番(1926.5.12、ニコライ・マルコ指揮)、第2番(1927.12.5)などを初演している。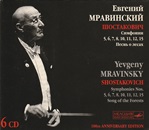 彼のショスタコーヴィチの交響曲録音は、第5、第6、第7、第8、第10、第11、第12、第15の8曲しかない。これらをいっぺんに入手しようという場合には、2004年夏にムラヴィンスキー生誕100年記念で発売されたメロディア輸入盤BOX「MEL CD 10 00770」6枚組(写真右)がある。上記の第11番が海賊盤であることを指摘してくださった方が、同じメール内でこれの入手を勧めてくださったのでタワーレコードで入手した。
彼のショスタコーヴィチの交響曲録音は、第5、第6、第7、第8、第10、第11、第12、第15の8曲しかない。これらをいっぺんに入手しようという場合には、2004年夏にムラヴィンスキー生誕100年記念で発売されたメロディア輸入盤BOX「MEL CD 10 00770」6枚組(写真右)がある。上記の第11番が海賊盤であることを指摘してくださった方が、同じメール内でこれの入手を勧めてくださったのでタワーレコードで入手した。
(この6枚組は単売もされているようだ。その場合は「第5&森の歌」「第7」「第8」「第6・第10」「第11・12・15、2CD」という形になる。)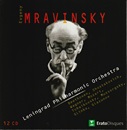 その後、2007年リリースされたERATO輸入盤BOX「ムラヴィンスキー・ライヴ録音集(2564 69890-5)」(写真左)を入手。ショスタコーヴィチ以外にもチャイコフスキー・ベートーヴェン・モーツァルト・ヴァーグナーなどの作品が入った12枚組である。その中に第5、第10、第12が収録されている。いずれも以前ERATOで単売されていた。
その後、2007年リリースされたERATO輸入盤BOX「ムラヴィンスキー・ライヴ録音集(2564 69890-5)」(写真左)を入手。ショスタコーヴィチ以外にもチャイコフスキー・ベートーヴェン・モーツァルト・ヴァーグナーなどの作品が入った12枚組である。その中に第5、第10、第12が収録されている。いずれも以前ERATOで単売されていた。
第12番はムラヴィンスキーの生涯最後の録音となったものである。(死の4年前の演奏だが、これ以後彼はすべての録音を拒否したという。)以下に、ムラヴィンスキーのショスタコーヴィチ録音をここに一覧の形で整理してみた。
曲 録音データ CD番号 第5番 1954年4月24日、レニングラード、MONO MEL CD 10 00770 1973年5月26日、東京文化会館、Live、Stereo Altus ALT002 1978年6月12日、ウィーン楽友協会、Live、Stereo Altus ALT289 1984年4月4日、レニングラード・フィルハーモニー大ホール、Live、Stereo ERATO 2564 69890-5 第6番 1952年、モノラル録音 (不所持) 1965年2月25日、モスクワ音楽院大ホール、Live、Stereo (不所持) 1972年1月27日、モスクワ音楽院大ホール、Live、Stereo MEL CD 10 00770
SCRIBENDUM SC 034第7番
「レニングラード」1953年2月26日、モスクワ放送スタジオ、MONO(唯一の録音) BMG 74321 29405 2
MEL CD 10 00770第8番 1947年6月2日、レニングラード、MONO BMG 74321 29406 2(不所持) 1960年9月23日、ロイヤル・フェイティヴァル・ホール、Live、Stereo
イギリス初演BBC LEGENDS BBCL-4002-2 1961年2月25日、レニングラード・フィルハーモニー大ホール、Live、Mono
(Stereo表記だが)MEL CD 10 00770 1982年3月28日、レニングラード、Live、Stereo PHILIPS PROA-31 第10番 1954年、モノラル録音 (不所持) 1976年3月3日、レニングラード・フィルハーモニー大ホール、、Live、Stereo ERATO 2564 69890-5 1976年3月31日、レニングラード・フィルハーモニー大ホール、Live、Mono
(Stereo表記だが)MEL CD 10 00770 第11番
「1905年」1959年2月2日、モスクワ放送スタジオ、MONO(唯一の録音) MEL CD 10 00770 第12番
「1917年」1961年10月、モスクワ放送スタジオ、Stereo MEL CD 10 00770 1984年4月30日、レニングラード・フィルハーモニー大ホール、Live、Stereo
(ムラヴィンスキー最後の録音)ERATO 2564 69890-5 第15番 1976年5月26日、レニングラード・フィルハーモニー大ホール、Live、Stereo BMG 74321-25192-2
MEL CD 10 00770ムラヴィンスキーの録音は、ショスタコーヴィチに限らずいろいろな形でCD化され、同録音異番号も多いと思われる。それだけでなく、旧ソ連ということもあり著作権そっちのけの悪質な海賊盤もあるようだ。その筆頭はRussian Discだ。このレーベルに対してはムラヴィンスキー夫人も激怒されているらしい。
他にも、以前このページに「第11番、PRAGAレーベル、1967年、チェコ・ラジオによるモノラル録音」を名盤と紹介していたものが、実はムラヴィンスキーの同曲唯一の録音である59年モノラル・スタジオ録音を偽ったものである、ということをある方がメールで指摘して下さった。このCDには「DIAPASON5」「CHOC」「ffffTelerama」のシールが貼られているのだが、それでもこういうことがあるのである。正規メロディア盤と比較すると音像もそっくり、タイムもそっくりである。終楽章だけ20秒ほど長いと思ったら、最後に盛大な拍手の音を貼り付けているのだ。悪質と言えば悪質だが、それが違和感が無いほど、演奏の最後の盛り上がりが素晴らしい、というのも皮肉な話だ。
またICONというレーベルも、かなり音質の良いCDを出していた。第5番は後にERATO盤BOXで出た1984年録音と同じもの、1983年表記の第8番はPHILIPS盤(1982年)と同じものである。どちらもタイム比較して確認した。こうした海賊盤とは別に、BBC LEGENDSからは貴重なライヴ録音が出ている。60年ロンドンでの第8番はこの曲のイギリス初演の録音である。雰囲気から推測するにプロムスでのライヴのようだ。(2枚組でもう1枚は同日演奏のモーツァルト第33番。)
- ヘルベルト・ケーゲル指揮ライプツィヒ放送交響楽団
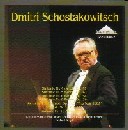
-
WEITBLICK。次の7曲が収録された5枚組SSS0040-2。全てライヴ録音。
場所は第5以外はライプツィヒ、コングレスハレである。DRA音源。
第4番----1969年5月20日、モノラル録音
第5番----1986年10月7日、東ベルリン、シャウシュピールハウスでのライヴ録音
第6番----1973年9月25日
第9番----1978年5月9日
第11番「1905年」----1958年4月24日、モノラル録音
第14番「死者の歌」----1972年3月28日、エミリア・ペトレスク(S)、フレッド・テシュラー(Bs)(ドイツ語歌唱)
第15番----1972年11月7日
東ドイツが消滅した直後にピストル自殺したケーゲルが、これらの曲をどのようにとらえていたのであろうか。また、これより先に、単品SSS0028-2で第7番「レニングラード」も出ている。
- ヴァレリー・ポリャンスキー指揮ロシア国立交響楽団
-
CHANDOS。
チャイコフスキーで名演を録音したポリャンスキーは、これまで8枚8曲のショスタコーヴィチの交響曲をリリースしている。
いずれも抒情的で品位のある演奏で、熱くなりすぎないのがショスタコの曲にふさわしいものになっている。CHANDOSレーベル特有の音の良さも特筆すべきであろう。
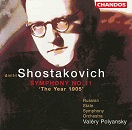
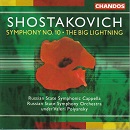
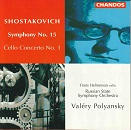
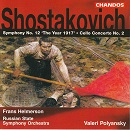
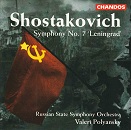
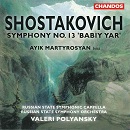
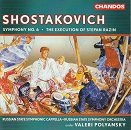
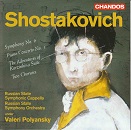
CHAN 9476----第11番「1905年」(1995年11月録音)
CHAN 9522----第10番(1995年6月録音)&「The Big Lightning」(2000年録音)
CHAN 9550----第15番(1996年3月録音)&チェロ協奏曲第1番(フランス・ヘルマーソン,Vc)
CHAN 9585----第12番「1917年」(1996年3月録音)&チェロ協奏曲第2番(同上)
CHAN 9621----第7番「レニングラード」(1996年10月録音)
CHAN 9690----第13番「バービ・ヤール」(1996年11月録音、Ayik Martyrosyan, Bass)
CHAN 9813----第6番(1999年6月録音)&「ステパン・ラージンの処刑」(2000年6月録音)
CHAN 10378---第9番&ピアノ協奏曲第1番(タチアナ・ポリャンスカヤ)他(2003年6月録音)
第10番とカップリングの「The Big Lightning」は未完のオペレッタ作品で、1980年にロジェストヴェンスキーがそのうち9つのナンバーのスコアを発見するまでは知られざる存在だった。第9番とカップリングのピアノ協奏曲のソロはポリャンスキーの娘である。このオケは英語でRussian State Symphony Orchestraと表記されているが、もとは82年にロジェストヴェンスキーのために組織された「ソヴィエト国立文化省交響楽団」である。ソヴィエト崩壊後、ポリャンスキーが設立・指揮していたソヴィエト国立文化省室内合唱団と合併して、オケ・合唱の複合体である「ロシア国立シンフォニー・カペラ(State Symphony Capella of Russia)」となった。92年からロジェストヴェンスキーの弟子であるポリャンスキーが指揮している。ロシア国立交響楽団はオケの録音時の名称である。
- ヴァレリー・ゲルギエフ指揮キーロフ管弦楽団
-
PHILIPS。ゲルギエフはPHILIPSから4枚5曲録音をリリースしている。
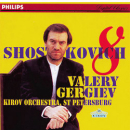
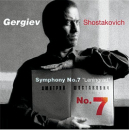
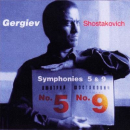

左から順に、
446 062-2(mercariで売却)----第8番(1994年9月、コンセルトヘボウでの録音)
UCCP-1073----第7番「レニングラード」(2001年9月19-21日、ロッテルダム・フィルとの合同演奏会ライヴ)
475 065-2----第5番(2002年6月30日、フィンランド、ミッケリでのライヴ録音)&第9番(2002年5月14-18日、マリインスキー劇場でのライヴ録音)
UCCP-1094(mercariで売却)----第4番(2001年11月20-22日、マリインスキー劇場でのライヴ録音)
第4番の解説に次のような内容が載っている。このオケに関係があるので紹介する。
1934年12月1日、にスターリンのライバルと目されていたレニングラードの共産党指導者で政治局員のセルゲイ・キーロフが暗殺された。これは36年から始まるスターリンの大粛清の前兆とされている事件である。(犯人の青年レオニード・ニコラエフはスターリンの命令によって暗殺を実行したと考えられている。)しかしこの事件をきっかけに、レニングラードのマリインスキー劇場がキーロフ劇場と改称したのであった。要するに、スターリンによる陰謀を覆い隠すためだったのだろう。ソ連崩壊の1991年に劇場名はマリインスキー劇場に戻されたので、本来ならこの録音のオケ名もマリインスキー管弦楽団でなくてはならないのだが、PHILIPSはずっとキーロフ管と表記していた。
ちなみに上記の事件とほぼ同じ頃、1934年11月から36年4月にかけて作曲されたのが第4番である。しかしその間にショスタコーヴィチに対して「社会主義リアリズムに反する」という批判がなされて、初演は作曲者自ら延期した。
第15番
第1楽章に「ウィリアム・テル」序曲、第4楽章ではヴァーグナーなどを引用。戦争や社会主義の政治・社会・経済への厳しい風刺をしてきたショスタコーヴィチだが、最後は「諸君、喝采したまえ、喜劇は終わった」と言っているかのような曲で終えたというのも面白い。
- クルト・ザンデルリンク指揮クリーヴランド管弦楽団
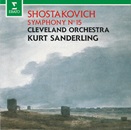
-
ERATO。1991年録音。予想通り丁寧な仕上げの演奏。
- エフゲニ・ムラヴィンスキー指揮レニングラード・フィル
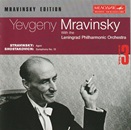
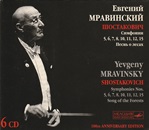
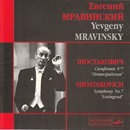
-
メロディア。1976年5月26日、レニングラード・フィルハーモニー大ホールでのステレオ・ライヴ録音。
左からBMGメロディア輸入盤、メロディアBOX、同単売(第11・12番とセット)。
第14番「死者の歌」
1969年9月29日、ルドルフ・バルシャイ指揮モスクワ室内管弦楽団、マルガリータ・ミロシニコワ、エフゲニー・ウラジミロフで初演された。全11楽章からなる、マーラー「大地の歌」と同じ歌曲集のような交響曲である。
- ムスティスラフ・ロストロポーヴィッチ指揮モスクワ・フィルハーモニー交響楽団ソロイスツ・アンサンブル
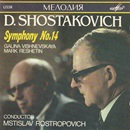
ガリーナ・ヴィシネフスカヤ(S)、マルク・レシェティン(B) -
メロディア。KKCC-6003。1973年2月、モスクワ音楽院大ホールでのスタジオ録音。
キングレコードからの国内盤仕様なので、日本語解説と歌詞の日本語訳が載っている(ただしロシア語歌詞は載っていない)。「1991年ソ連製CD(MADE IN USSRと記載)」なのも骨董的価値あり。
音質も良く、ロストロポーヴィチ夫人のヴィシネフスカヤが歌っているので、上記全集にもこの曲だけはこの録音を収録したのだろう。全集を入手したので当単売CDはmercariで売却。 - ルドルフ・バルシャイ指揮モスクワ室内管弦楽団、マクワラ・カスラシヴィリ、エフゲニー・ネステレンコ

-
TOKYO FM。1975年5月16日、東京文化会館ライヴ。
世界初演指揮者による日本初演の貴重な録音である。
第13番「バビ・ヤール」
1962年12月18日、モスクワ音楽院大ホールにて、キリル・コンドラシン指揮モスクワ・フィルハーモニー管弦楽団、ロシア共和国合唱団&グネーシン音楽大学合唱団、ヴィタリー・グロマツキー(B)で初演された。第1楽章「バビ・ヤール」、第2楽章「ユーモア」、第3楽章「商店で」、第4楽章「恐怖」、第5楽章「出世」の5楽章とも、エフトゥシェンコの詩をバスと男声合唱が歌う形式である。だから本来は、ナチスによるユダヤ人虐殺の地名「バビ・ヤール」は第1楽章の表題だったのだが、やがて交響曲全体の表題になった。それ以外もソ連の政治・社会・経済の実態を風刺した内容である。初演後、第1楽章の歌詞を4行ずつ2カ所修正するよう共産党政府から指示された。
しかし、1970年1月にオーマンディ指揮フィラデルフィア管弦楽団による“ソ連圏外”での初演(およびその後の録音)では、オリジナルの歌詞で歌った。
- キリル・コンドラシン指揮バイエルン放送交響楽団・男声合唱団

ジョン・シャーリー=カーク(B) -
PHILIPS。1980年12月18-19日、ヘルクレスザールでのライヴ録音。
上記のようにコンドラシンは当曲の初演指揮者である。初演後、モスクワ・フィルとの全集録音では第1楽章を修正した歌詞で録音していた。
しかし西側に亡命後のこの演奏では、オリジナルの歌詞で歌っている。
第12番「1917年」
- ミヒャエル・ギーレン指揮南西ドイツ放送交響楽団
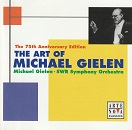
-
ARTE NOVA。1989年9月録音。ギーレン録音集4枚組に収録。ベルリンの壁が崩れる直前の録音である。
- エフゲニ・ムラヴィンスキー指揮レニングラード・フィル
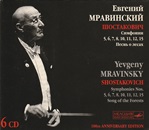
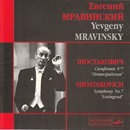
-
メロディア。1961年10月、モスクワ放送スタジオ・ステレオ録音。
ソ連の場合、この年代でモノラルでもおかしくなかったが、よくステレオ録音してくれていたものだ。 - エフゲニ・ムラヴィンスキー指揮レニングラード・フィル
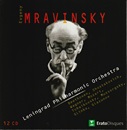
-
ERATO。1984年4月30日、レニングラード・フィルハーモニー大ホールでのライヴ録音。
ムラヴィンスキー最後の録音である。1988年の死の4年前のことであるが、彼は以後の録音を一切拒絶したという。
第11番「1905年」
- エフゲニ・ムラヴィンスキー指揮レニングラード・フィル
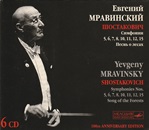
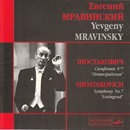
-
メロディア。1959年2月2日、モスクワ放送スタジオでのモノラル録音。
ムラヴィンスキーの同曲唯一の録音である。モノラルだが音質は良く、演奏も素晴らしい。(上記の通り、PRAGA盤はこれの最後に拍手の音を貼り付けている。) - 北原幸男指揮NHK交響楽団
-
KOCH。1992年ライヴ録音。国内盤は東芝EMIがKOCH原盤と明記して出していた。
結構いい演奏。北原はドイツの歌劇場の監督をしているが、ショスタコが好きなようである。(第5番の録音がAltusから出た。)mercariで売却した。 - アンドレ・クリュイタンス指揮フランス国立放送管弦楽団
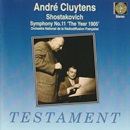
-
TESTAMENT。1958年5月、作曲者立ち会いのもとでのステレオ録音。
この曲はモスクワで1957年10月30日に初演されたばかりであり、異例のスピード初録音ということになる。
それにしても、クリュイタンスがロシア物も得意なのは知っていたが、まさかショスタコまで録音しているとは思わなかった。→mercariで売却。「伴奏指揮者としてのクリュイタンス」というタイトルのEMI輸入盤4枚組(チッコリーニのチャイコフスキーPC.No.1、フランソワのプロコフィエフPC.No.3、タッキーノのラフマニノフPC.No.2など収録)に何とショスタコーヴィチ自身をソリストに迎えたピアノ協奏曲第2番の1958年モノラル録音が収録されている。
- レオポルド・ストコフスキー指揮ヒューストン交響楽団
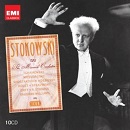
-
EMI。ストコフスキーのCapitol録音集BOX。1958年録音。
ストコフスキーは第6番のアメリカ初演を行っている。この曲も前項に書いたとおり初演直後の録音である。同時代の音楽の紹介につとめていた、という彼の一面がわかる真面目な演奏だ。
第10番
- エフゲニ・ムラヴィンスキー指揮レニングラード・フィル
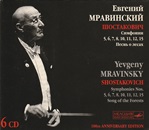
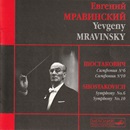
-
メロディア。22:22,5:33,11:10,11:28。
1976年3月31日、レニングラード・フィルハーモニー大ホールでのライヴ録音。
この曲はメロディアが1954年にモノラル・スタジオ録音を残しているが、私は所持していない。
単売では第6番とカップリング。 - エフゲニ・ムラヴィンスキー指揮レニングラード・フィル
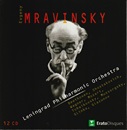
-
ERATO。1976年3月3日、レニングラード・フィルハーモニー大ホールでのライヴ録音。
22:04,3:59,10:56,11:09。同年同月の演奏だから、解釈など変わりようもないので、タイムも似るのは当然だが、比較してみると有意な差があるので、別録音ということでよいだろう。 - スタニスラフ・スクロヴァチェフスキ指揮ハレ管弦楽団

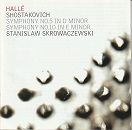
-
HALLE。1990年11月23-24日、ボルトン、アルバート・ホールでの録音。
超名演の第5番とカップリングで2枚組。もともとはPickwickによる録音。 - ディミトリ・ミトロプーロス指揮ニューヨーク・フィル
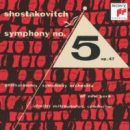
-
SONY。SICC-1601/2。1954年10月18日、モノラル録音。
前年12月17日にムラヴィンスキーが初演して1年たたないうちの録音である。
第5番、およびエフレム・クルツ指揮の第9番とカップリング。 - カレル・アンチェル指揮チェコ・フィル
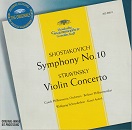
-
DG。OIBP化。1955年10月、ミュンヘン、ヘルクレスザールにおけるモノラル録音。
アンチェル指揮ベルリン・フィル、シュナイダーハンによるストラヴィンスキーのヴァイオリン協奏曲(1962年ステレオ)とカップリング。 - ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮ベルリン・フィル
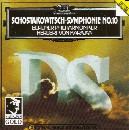
-
DG。OIBP化。1981年録音。
カラヤンのこの曲2度目の録音である。なんでまたこの曲だけ2回も録音したのだろう? - ダヴィッド・オイストラフ指揮ベルリン交響楽団
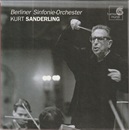
-
HMF。HMX 2905255/9(5CD)。1972年9月29日、ベルリン国立歌劇場ライヴ。
このオケのシェフだったザンデルリンクの引退を記念した5枚組であるが、オイストラフがヴァイオリンのソリストで共演したプロコフィエフの協奏曲第1番・第2番、ストラヴィンスキーの協奏曲ニ長調といった曲も収録されているためか、彼の指揮した曲も収録されている(他にシューベルトの交響曲第2番、ベートーヴェンのロマンス第1番)。
オマケで収録されているわりには、この曲でのオイストラフの指揮はなかなか素晴らしい。
第9番
- セルジュ・チェリビダッケ指揮スウェーデン放送交響楽団
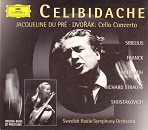
-
DG。1971年3月ライヴ録音。OIBP化。
チェリは晩年はスローテンポのブルックナーが売りだったが、もともとはこういう現代的な曲が得意だった人である。
(LDでプロコフィエフの古典交響曲のリハーサル風景が出ている。) - セルジュ・チェリビダッケ指揮ミュンヘン・フィル
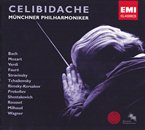
-
EMI。正規発売第4弾BOX TOCE-55661/74。1990年2月9日のライヴ。
もちろん、晩年においてもこういう曲をやる時は、ブルックナーとは違う適切なテンポで名演を聴かせていた。
下記第1番、およびバーバー「弦楽のためのアダージョ」とカップリング。 - セルジュ・チェリビダッケ指揮スウェーデン放送交響楽団
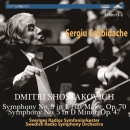
-
WEITBLIK。1964年11月20日、ヴァステロース(ストックホルムの西にある)でのライヴ録音。
息子の許可をとっての正規発売で、67年の第5番とカップリングである。 - ベルナルト・ハイティンク指揮ロンドン・フィル
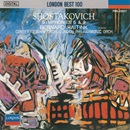
-
DECCA。1980年録音。廉価盤でコンセルトヘボウとの第5番とカップリング。
- ゲオルク・ショルティ指揮ウィーン・フィル
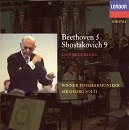
-
DECCA。1990年5月ライヴ。ベートーヴェン「運命」とのカップリング。
- フェレンツ・フリッチャイ指揮ベルリン放送交響楽団
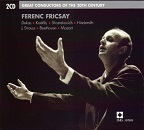
-
EMI。GREAT CONDUCTORS OF THE 20TH CENTURYシリーズ輸入盤。
1954年4月30日、5月3日、RIASによるイエス・キリスト教会でのライヴ録音(放送用録音)。 - エフレム・クルツ指揮ニューヨーク・フィル
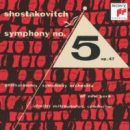
-
SONY。SICC-1601/2。1949年4月8日、モノラル録音。
この曲の初の商業用録音である。ミトロプーロス指揮の第5番、第10番とカップリング。
第8番
- エフゲニ・ムラヴィンスキー指揮レニングラード・フィル
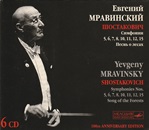
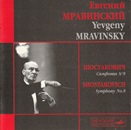
-
メロディア。
1961年2月25日、レニングラード・フィルハーモニー大ホールでのライヴ録音。
当CDには「ステレオ」と表記されているがモノラル録音である。 - エフゲニ・ムラヴィンスキー指揮レニングラード・フィル
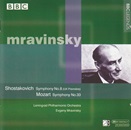
-
BBC LEGENDS。
1960年9月23日、ロイヤル・フェイティヴァル・ホールでのステレオ・ライヴ録音。
当曲のイギリス初演の記録である。同日演奏のモーツァルト第33番とカップリング2枚組。 - エフゲニ・ムラヴィンスキー指揮レニングラード・フィル
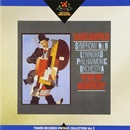
-
PHILIPS。1982年3月28日、レニングラードでのライヴ録音。
西側レーベルからの正規発売でCD化もされた。しかしPHILIPSがDECCAに吸収されてしまったこともあり、入手困難になってしまい、そこに海賊盤が入り込む隙も生まれた。ICONレーベルは「1983年」と表記していたが、PHILIPS盤と同一録音である。
私はTOWER RECORDSの企画で復活したPHILIPS盤を入手。
第6番
- エフゲニ・ムラヴィンスキー指揮レニングラード・フィル
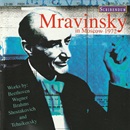
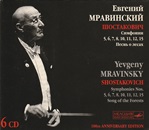
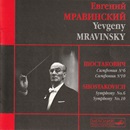
-
SCRIBENDUM。「1972年1月モスクワ・ライヴ3枚組」。
1972年1月27日、モスクワ音楽院大ホールでのステレオ・ライヴ録音。
メロディア盤BOXにも収録されている。単品では第10番とカップリング。なお、「1965年2月25日、モスクワ音楽院大ホールでのステレオ・ライヴ録音」というのも正規発売されていたことがあるようだが、私は所持していない。
第1番
- ジャン・マルティノン指揮ロンドン交響楽団
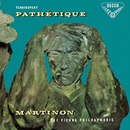
-
DECCA。タワーレコード企画SACD-Hybrid国内盤。
1957年12月、キングズウェイ・ホールでの録音。
メインはウィーン・フィルとの「悲愴」である。 - レオポルド・ストコフスキー指揮シンフォニー・オブ・ジ・エア
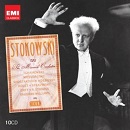
-
EMI。ストコフスキーの録音集BOX。United Artists原盤。
1958年12月録音。LPのカップリング曲である「前奏曲とフーガ変ホ短調」(ストコフスキー編)、「ムツェンスク群のマクベス夫人」から前奏曲も収録している。 - カレル・アンチェル指揮チェコ・フィル
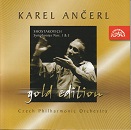
-
SUPRAPHON。1964年4月7-10日録音。
名曲の名演である。カップリングの第5ともども素晴らしい。
アンチェルは他に「レニングラード」(MONO)、及びチェロ協奏曲第1番(Milos Sadlo、1968年6月=「プラハの春」真っ最中の録音)を残している。 - セルジュ・チェリビダッケ指揮ミュンヘン・フィル
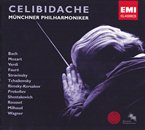
-
EMI。正規発売第4弾BOX TOCE-55661/74。1994年5月31日,6月2,3日のライヴ。
上記第9番、およびバーバー「弦楽のためのアダージョ」とカップリング。 - レナード・バーンスタイン指揮シカゴ交響楽団
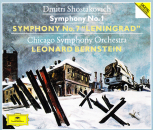
-
DG。1988年ライヴ録音。第7番とのカップリング。
- ハワード・ミッチェル指揮ナショナル交響楽団
-
ウェストミンスター。1953年モノラル録音。ロジンスキ指揮の第5とカップリング。