J・S・バッハの協奏曲
バッハの協奏曲作品として、BWV目録には次のものがあげられている。
(Vn=ヴァイオリン、Ob=オーボエ、fl=フルート、Cem=チェンバロ、K=クラヴィア)
「クラヴィア」は、普通チェンバロを使用するが、しかし現代ピアノを使った演奏もあるので、クラヴィアと記した。
| 作品 | 調 | BWV | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vn協 | Nr.1 | a | 1041 | → | K協.Nr.7 g-moll BWV.1058 |
| Nr.2 | E | 1042 | → | K協.Nr.3 D-dur BWV.1054 | |
| 2Vn協 | d | 1043 | → | 2K協 c-moll BWV.1062 | |
| 三重協奏曲 (fl,Vn,Cem) | a | 1044 | ← |
クラヴィア曲「前奏曲とフーガBWV.894」を第1,3楽章に、 オルガン曲「トリオ・ソナタNr.2 BWV.527」を第2楽章に編曲。 | |
| 協奏曲楽章断片 (Vn,3tp,2ob) | D | 1045 | ← | 教会カンタータのシンフォニアの編曲? | |
| ブランデンブルク協奏曲 第1-6番 BWV.1046-51 但し、第1番は、初稿 BWV.1046a (=BWV.1071)も存在する。 | |||||
| K協 | Nr.1 | d | 1052 | ← | V協 d-moll BWV.1052a (復元) |
| Nr.2 | E | 1053 | ← | Ob協 F-dur BWV.1053a (復元、Es-durの可能性も) | |
| Nr.3 | D | 1054 | ← | V協 Nr.2 BWV.1042 | |
| Nr.4 | A | 1055 | ← | オーボエ・ダモーレ協 A-dur BWV.1055a (復元) | |
| Nr.5 | f | 1056 | ← |
V協 g-moll BWV.1056a (復元)。但し本当の原曲では 第2楽章はカンタータBWV.156のシチリアーノ。 | |
| Nr.6 | F | 1057 | ← |
ブランデンブルク協 Nr.4 BWV.1049を 2本のブロックフレーテとチェンバロのための協奏曲に編曲したもの | |
| Nr.7 | g | 1058 | ← | V協 Nr.1 BWV.1041 | |
| Nr.8 | d | 1059 | ← |
冒頭9小節の断片のみ。カンタータBWV.35から復元。 原曲はOb協 BWV.1059a(復元、但し第2楽章はBWV.1056使用) | |
| 2K協 | c | 1060 | ← |
Ob・Vn協 BWV.1060a (復元、c-moll, d-mollの2種ある。) いろいろある復元曲の中では最もメジャーなもの。他に2Vn協 d-mollもある。 | |
| C | 1061 | 新作 | |||
| c | 1062 | ← | 2Vn協 BWV.1043 | ||
| 3K協 | d | 1063 | ← | 原曲は不明。 | |
| C | 1064 | ← | 3Vn協 D-dur、Fl・Ob・Vn協 D-dur の2通り復元されている。 | ||
| 4K協 | a | 1065 | ← | ヴィヴァルディ「調和の霊感」op.3-第10曲 h-moll (4Vn協) | |
クラヴィア協奏曲
オリジナル楽器の決定盤は、コープマンがエラートに録音した大全集と考えているが、入手していない。
- カール・リヒター(cemb,指揮)ミュンヘン・バッハ管弦楽団
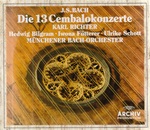
-
ARCHIV。輸入盤 439 612-2。1971-2年録音。全集である(BWV.1059は除く)。
- チェンバロ協奏曲全曲 BWV.1052-1058
- 2台のチェンバロのための協奏曲 BWV.1060-1062(+ ヘトヴィヒ・ビルグラム)
- 3台のチェンバロのための協奏曲 BWV.1063-1064(+ アイオナ・フュッテラー)
- 4台のチェンバロのための協奏曲 BWV.1065(+ ウルリケ・ショット)
重厚なオーケストラと遅めのテンポは、一昔前の「ドイツ3大B」の典型的演奏スタイルである。
「BWV.1059」が含まれていないのは、曲の「素性」を気にしたからだろう。 - カール・リステンパルト指揮ザール室内管弦楽団
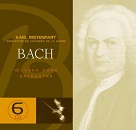
Fritz Neumeyer, Lili Berger, Konrad Burr, Ilse Urbuteit -
ACCORD。1962年録音。
2001年末に、リステンパルトのバッハ録音集6枚組BOXが96kHz-24bitリマスターされて発売されたのを入手。(ACCORDもユニバーサル傘下に入ったようだ。)
収録曲は、2台の協奏曲 BWV.1062、3台の協奏曲 BWV.1063-1064、4台の協奏曲 BWV.1065である。モダン・チェンバロ使用でソリスト名は4名併記されている。 - 渡邊順生、ザ・バロック・バンド
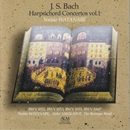
-
ALM RECORDS。製造・販売:コジマ録音。ALCD-1034。2001年2月27日〜3月1日、録音。
BWV.1052, 1053, 1055、および2台のためのBWV.1060(+崎川晶子)。
ザ・バロック・バンドは、渡邊順生と宇田川貞夫(渡邊のゴルトベルク変奏曲をリリースしているセシル・レコードの代表でもある)によって1984年に設立されたオリジナル楽器のオーケストラであるが、この録音では各パート1人である(Vn2, Vla, Vc, Violoneの5人)。
渡邊氏自身による詳細な解説付きである。その中で彼は「古楽器による演奏をもってしても、チェンバロ協奏曲だけは、なんでバッハがこんなバランスの悪い編成の曲を書いたのか首をかしげてしまうことがしばしばである」と書いている。そして「おそらくライプツィヒでコレギウム・ムジクムの演奏会場であったコーヒー・ハウスの音響が、チェンバロの音がよく響く構造だったのだろう」と推測されている。氏は、演奏会場では決してあり得ないようなイコライジング処理は行わず、マイクの位置を工夫することだけでこの録音を行った。時々チェンバロのメロディが弦に隠れそうになってしまうが、これが生演奏のベストの状況に近い録音といえるもののようである。使用楽器は、ゴルトベルク変奏曲の録音で用いたのと同じスコヴロネック製作のコピーである。 - グスタフ・レオンハルト(cemb)指揮レオンハルト・コンソート(BWV.1053-58,1064)
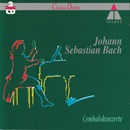
ヘルベルト・タヘッツィ、ニコラウス・アーノンクール指揮コンツェントゥス・ムジクス・ヴィーン(BWV.1052) -
TELDEC。WPCS 4103/4(4509-95250-2)。1961-69年頃の録音。
レオンハルトが、ここで録音しなかったBWV.1052は、後にセオンに録音している。BWV.1064 は、アンネッケ・ヴィッテンボッシュ、アラン・カーティスとの共演である。
また、BWV.1057ではフランス・ブリュッヘンがブロックフレーテを吹いている。録音がややオンマイク気味で、オリジナル楽器の高い倍音をとらえられていないのが残念。 - セルジオ・チオメイ(cem)、エウロパ・ガランテ
-
Virgin。1999年録音。BWV.1054のみ。
メインは復元されたVn協3曲(ビオンディ)である。下参照。 - エトヴィン・フィッシャー(piano,指揮)フィッシャー室内管弦楽団
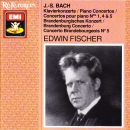
-
EMI。Referenceシリーズ輸入盤。CDH7 63039 2。1930年代録音。
BWV.1052,1055,1056の3曲。
ブランデンブルク第5番とのカップリング。 - エトヴィン・フィッシャー(piano,指揮)フィルハーモニア
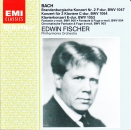
-
EMI。Referenceシリーズ輸入盤。CDH7 64928 2。1950年録音。
BWV.1053は、このCDが初リリースとなる。
3台の協奏曲BWV.1064は、ロナルド・スミス、デニス・マシューズとの共演である。
ブランデンブルク第2番、その他クラヴィア曲(半音階的幻想曲とフーガなど)とのカップリング。 - ディヌ・リパッティ(piano)、エドゥアルト・ファン・ベイヌム指揮コンセルトヘボウ
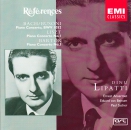
-
EMI。1947年10月2日ライヴ。BWV.1052(ブゾーニ編)
2001年初め、ART処理された輸入盤CDH5 67572 2で初めて日の目を見た録音である。
録音は時代の割には大変良好で、リパッティの素晴らしく格調高い音色を聴ける。
カップリングはこれもまた初登場ライヴの協奏曲でリスト第1番、バルトーク第3番の2曲である。 - オリ・ムストネン(p,指揮)、ドイツ・カンマーフィル
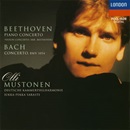
-
DECCA。1993年6月、ブメーメン放送局での録音。
ピアノ協奏曲第3番BWV.1054。
メインはベートーヴェンのヴァイオリン協奏曲をベートーヴェン自身がピアノ協奏曲に編曲したもの。バッハとベートーヴェンがそれぞれ自らV協をP協に編曲した2曲によるアルバムである。mercariで売却。
ヴァイオリン協奏曲
ここは、BWV.1041, 1042, 及び1043(2Vn)を中心としたディスクをあげる。
- 寺神戸亮、鈴木雅明指揮バッハ・コレギウム・ジャパン

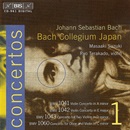
若松夏美(第2Vn)、マルセル・ポンセール(ob) -
BIS。1998年録音。BWV.1041,1042, 2Vn協BWV.1043、
及びオーボエとVnのための協奏曲BWV.1060a。
2Vn協BWV.1043の録音において、彼らは最小限の人数での演奏を選択した。それは独奏の2人を除くオケは、Vn2,Vla,Vc,cb,cembの計6人というものである。これはこの曲の現存最古の手稿譜に「6声のコンチェルト」書いてあるとおり、2つのVnを軸としながらも全ての声部がコンチェルタンテ的性格を持っているからである。(他の曲ではオケは第1Vn2名,第2Vn2名の他はVla,Vc,cb,cemb各1名。当然cembは鈴木雅明、Vcは鈴木秀美である。) - アンドルー・マンゼ(Vn)指揮アカデミー・オヴ・エンシェント・ミュージック

レイチェル・ポッジャー(第2Vn) -
HMF。1996年録音。BWV.1041,1042, 2Vn協BWV.1043。
他に、復元曲の2Vn協 d-moll BWV.1060も収録。
おそらく、下にあげた様々なオリジナル楽器演奏の中でも最もモダンな躍動感のある演奏と思われる。編成はcb,cemb以外は上のBCJ盤の2倍の人数である。(すなわち4,4,2,2,1,1) - ジギズヴァルト・クイケン(Vn)指揮ラ・プティット・バンド、ルーシー・ファン・ダール(第2Vn)
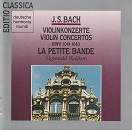
-
DHM。1981年録音。
BWV.1041,1042, 2Vn協BWV.1043。他に、ホグウッド&シュレーダー、アーノンクール夫妻、ピノック&スタンデイジ、
コープマン&ハジェットなどといったものが出ているが、いずれも所持していない。 - イェフディ・メヌーヒン(Vn),ジョルジュ・エネスコ指揮パリ交響楽団
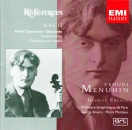
-
EMI。Referenceシリーズ輸入盤。1932〜36年録音。BWV.1041,1042, 2Vn協BWV.1043。
BWV.1043では、第2Vnがジョルジュ・エネスコ、指揮はピエール・モントゥーである。
1999年末、バッハ没後250年を前にART処理された輸入盤がリリースされたので買い直した。 - ダヴィッド・オイスラフ(Vn)指揮ウィーン交響楽団
イーゴリ・オイストラフ(第2Vn)、ユージン・グーセンス指揮ロイヤル・フィル -
DG。1962年、1961年録音。OIBP化。BWV.1041,1042, 2Vn協BWV.1043。
チャイコフスキーとブラームスの協奏曲(コンヴィチュニー指揮DSK、MONO)や、ベートーヴェンの「ロマンス」とカップリングの2枚組。 - カール・リヒター指揮ミュンヘン・バッハ管弦楽団、オットー・ビュヒナー、クルト・グントナー
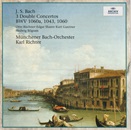
-
ARCHIV。POCA 3070。1963年録音。2Vn協BWV.1043のみ。
Vn・Ob協奏曲BWV.1060a、2台のチェンバロ協奏曲第1番BWV.1060とカップリング。
下記参照。(復元された3Vn協奏曲もある。) - ヨゼフ・シゲティ、カール・フレッシュ、ワルター・ゲール指揮管弦楽団

-
opus蔵 OPK 2030。1937年、ColumbiaSP録音復刻。2Vn協BWV.1043
ともに多くの門下生がいる2人の共演である。
カップリングはシゲティの無伴奏ソナタ第1番・第2番。 - イェフディ・メヌーヒン、ジョージ・マルコム指揮イギリス室内管弦楽団
-
BBC LDGENGS。1963年6月23日、オールドバラ音楽祭ライヴ録音。BWV.1042。
64年録音のメンデルスゾーン及びブラームス二重協奏曲(ロストロポーヴィッチ)とカップリング。 - トマス・ブランディス、クラウス・テンシュテット指揮ベルリン・フィル
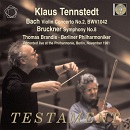
-
TESTAMENT。JSBT2 8447。1981年11月21日、フィルハーモニーでのライヴ録音。BWV.1042。
同日演奏のブルックナー交響曲第8番とカップリングで2枚組である。 - アンネ=ゾフィー・ムター(Vn)、ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮ベルリン・フィル

-
SONY。C-major(テレモンディアル)。BWV.1042。
1984年12月31日、ベルリン、フィルハーモニーでのライヴ収録。
ライヴ一発撮りなので、おかしな演出は無い。カラヤンがチェンバロを弾きながら指揮している。カップリングは同日の「マニフィカト」、およびベートーヴェンのヴァイオリン協奏曲、ヴィヴァルディ「四季」。
復元された協奏曲
- カール・リヒター指揮ミュンヘン・バッハ管弦楽団
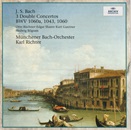

-
ARCHIV。国内盤で2枚分の録音がある。
2000年春、それらが国内盤でまとめて発売された。
(それ以前はブランデンブルク協奏曲や管弦楽組曲とカップリングになっていた。)POCA 3070(1963年録音)
Ob・Vn協 d-moll BWV.1060a---エドガー・シャン(ob)、オットー・ビュヒナー(v)
(2Vn協BWV.1043、2台のチェンバロのための協奏曲 BWV.1060とカップリング。)
POCA 3071(1980年録音)
オーボエ・ダモーレ協奏曲BWV.1055a---マンフレート・クレメント(Ob d'amore)
Fl・Vn・Cembのための三重協奏曲BWV.1044---オーレール・ニコレ(Fl)、ゲルハルト・ヘッツェル(Vn)、リヒター
3つのヴァイオリンのための協奏曲BWV.1064a---ヘッツェル、ヴァルター・フォルヒェルト、ルーベン・ゴンザレス - カール・リステンパルト指揮ザール室内管弦楽団
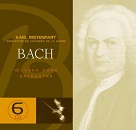
-
ACCORD。1960, 65年録音。管弦楽組曲全曲とカップリング。収録曲は次の2曲。
3つのヴァイオリンのための協奏曲BWV.1064a、Fl・Vn・Cembのための三重協奏曲BWV.1044。2001年末に、リステンパルトのバッハ録音集6枚組BOXが96kHz-24bitリマスターされて発売されたのを入手。(ACCORDもユニバーサル傘下に入ったようだ。)
- ニコラウス・アーノンクール指揮コンツェントゥス・ムジクス・ヴィーン
アリス・アーノンクール(Vn)、ユルク・シェフトライン(Ob) -
DG-UNITEL。輸入盤DVD2枚組。1982年7月8-13日、オクセンハウゼン修道院図書館での収録。
オーボエとVnのための協奏曲BWV.1060R c-moll。
メインはブランデンブルク協奏曲全曲である。 - ラインハルト・ゲーベル指揮ムジカ・アンティクァ・ケルン
-
ARCHIV。1987年録音。Fl・Vn・Cembのための三重協奏曲BWV.1044
ブランデンブルク協奏曲全曲にカップリングで収録されている。 - ファビオ・ビオンディ(Vn)指揮エウロパ・ガランテ、アルフレッド・ベルナルディーニ(Ob)
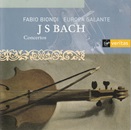
-
Virgin。1999年録音。
Ob・Vn協 c-moll BWV.1060a、Vn協 BWV.1052、同 BWV.1056。
BWV.1060aがd-mollではなくc-mollとなっている。
他に、クラヴィア協奏曲BWV.1054がカップリングされている。 - アカデミー・オヴ・エンシェント・ミュージック、アンドルー・マンゼ、レイチェル・ポッジャー(Vn)
-
HMF。1996年録音。2Vn協 d-moll BWV.1060。
普通、BWV.1060は、Ob・Vn協奏曲に復元されているが、これは新しい復元のようだ。
上記ヴァイオリン協奏曲BWV.1041-43にカップリングされている。 - 鈴木雅明指揮バッハ・コレギウム・ジャパン、寺神戸亮(Vn)、マルセル・ポンセール(ob)
-
BIS。1998年録音。オーボエとVnのための協奏曲BWV.1060a。
上記ヴァイオリン協奏曲BWV.1041-43にカップリングされている。