J・S・バッハ 音楽の捧げ物 (Musikalisches Opfer) BWV.1079
礒山雅氏の「バッハ 魂のエヴァンゲリスト」巻末の作品総覧における記述を引用する。
「音楽の捧げ物」を、厳しい精神性の音楽として受けとめようと思うならば、リヒター盤に勝るものはない。とくに、ニコレとビュヒナーの共演した「トリオ・ソナタ」の高貴で奥深い表現は素晴らしい。一方これをオリジナル楽器の演奏で聴くと、現実的な室内楽としての生気がクローズアップされてくる。(中略)レオンハルト夫妻とクイケン3兄弟の顔合わせによるセオン盤に、バロック音楽の精髄ともいうべき世界が展開されている。
これを読んで、一時期、SEON レーベルのCDを買いあさったものである。(同レーベルは最近BMGからソニーに移転した。)
- カール・リヒター盤
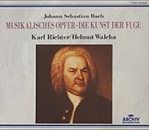
-
ARCHIV。1963年録音。
オーレール・ニコレ(Fl)、オットー・ビュヒナー(Vn)、クルト・グントナー(Vn)、ジークフリート・マイネッケ(Vla)、
フリッツ・キスカルト(Vc)、ヘトヴィヒ・ビルグラム(Cemb)、そしてリヒター(Cemb,指揮)の7人による演奏である。
リヒターは1台のチェンバロ用の曲を全てビルグラムにまかせており、彼がチェンバロを弾いているのは、最後のほうの3曲(2台のチェンバロによる4声の謎カノン、トリオ・ソナタ、無窮カノン)のみである。 - ニコラウス・アーノンクール指揮コンツェントゥス・ムジクス・ヴィーン
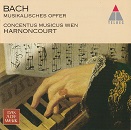
-
TELDEC。1970年録音。
ヘルベルト・タヘッツィ(Cemb)、レオポルト・シュタストニー(Fl)、アリス・アーノンクール(Vn)、ヴァルター・プファイファー(Vn)、クルト・タイナー(Vla)、ニコラウス・アーノンクール(Tenor Viola,Vc)の6人による演奏である。 - レオンハルト夫妻&クイケン3兄弟盤
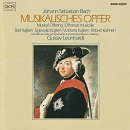
-
SEON。1974年11月、ドープスヘツィンデ教会での録音。
グスタフ・レオンハルト指揮&cemb、マリー・レオンハルト(vn)、ジギズヴァルト(Vn)、バルトルド(Fl)、ヴィーラント(gamba)、他にローベル・コーネン(cemb)が参加して計6人である。 - ラインハルト・ゲーベル指揮ムジカ・アンティクァ・ケルン
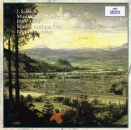
-
ARCHIV。1979年ADD録音。ここに挙げた5枚のCDのうち、これだけが曲順が違う。
ゲーベル(Vn)、ハーヨ・ベス(Vn)、チャールズ・メドラム(Vla da gamba)、ウィルベルト・ハーツェルツェト(Fl)、ヘンク・ボウマン(Cemb)の5人による演奏である。 - クイケン・アンサンブル

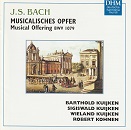
-
DHM。1994年新録音。
ジギズヴァルト,ヴィーラント,バルトルドの3兄弟にローベル・コーネン(cemb)が加わる4人だけである。 - クイケン・アンサンブル

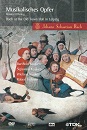
-
TDK。DVD。
同じメンバーによる2000年7月28日、没後250年の日にライプツィヒ旧市庁舎内ホールでのライヴ収録。
そもそも何で、こんなに編成が違うのか。それについては、詳細にこれらのCDに付属する解説を読み聴き比べた結果を、下に記しておく。
解説
1.曲順について
この曲のディスクには、演奏曲順が違うものもたくさんある。しかし、上の5枚のうちMAK盤を除く4枚は曲順については同じである。これは「新バッハ全集」が採用した曲順である。以下にそれを表記する。
| Ⅰ.3声のリチェルカーレ | |
| Ⅱ.王の主題による無限カノン | |
| Ⅲ.王の主題による各種のカノン | 1.2声の逆行カノン |
| 2.2声の同度のカノン※ | |
| 3.2声の反行カノン | |
| 4.2声の反行の拡大カノン | |
| 5.螺旋カノン | |
| Ⅳ.上方5度のカノン風フーガ | |
| Ⅴ.6声のリチェルカーレ | |
| Ⅵ.謎のカノン (尋ねよ、さらば見いださん) | 1.2声のカノン |
| 2.4声のカノン | |
| Ⅶ.トリオ・ソナタ | |
| Ⅷ.無限カノン | |
なお、初版印刷譜は次の3部にわかれていた。
第1部「タイトル、献辞、Ⅰ、Ⅱ」
第2部「Ⅶ、Ⅷ」
第3部「Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ」
この第3部には「Regis Iussu Cantio Et Reliqua Canonica Arte Resoluta」というタイトルがついている。これは直訳すると「王の命令で主題がカノンに作曲された楽曲と、その他はカノン技法で解決したもの」 となり、それはこの曲集全体にかかる記述である。またその各語の頭文字をとると「RECERCAR(リチェルカーレ)」となる。(B・クイケンによるクイケン盤の解説)
MAK盤では、「Ⅰ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅱ・Ⅷ・Ⅵ・Ⅶ・Ⅴ」の順で収録している。
そしてその最初と最後の「リチェルカーレ」に上の「Regis Iussu Cantio Et Reliqua Canonica Arte Resoluta」というタイトルを付している。
リヒター盤には東川清一氏の解説で次のように書いてある。
今日残っているこの曲の楽譜は、5線紙の紙質からみて少なくとも2つの部分からなっている。そして献辞とともに王に送付されたのはそのうちの1つで、もう1つの部分は後から王に送付された、と考えられる。先に送付されたのは「Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ」であり、それ以下は後から送付したものである。
これに続けて同解説では、楽器編成及び配列(=上記の曲順)におけるハインリヒ・フスマンの説を紹介し、リヒターはそれにもっとも忠実に行っている、という。
2.楽器編成について
この曲で楽器編成が指定されているのは、「Ⅶ.トリオ・ソナタ」「Ⅷ.無限カノン」のみで、それはフルート・ヴァイオリン・通奏低音(チェンバロ、ヴィオラ・ダ・ガンバもしくはチェロ)である。
楽器編成でまず問題となるのは、上で※印をつけたⅢの2である。この曲の題は初版では次のようである。
「Canon à 2 Violin : in Unisono」
この「Violin」の後の「:」は、「i」のミスプリント、もしくはその文字の省略形とされ、結局、複数形の「Violini」ということになっていた。つまり「2つのヴァイオリンによる同度のカノン」ということになる。リヒター盤、レオンハルト盤とも、その解釈である。
しかし、バルトルド・クイケンは最新録音盤において、上は印刷譜の誤りであり、
「Canon à 2 : Violin in Unisono」
と読むべきである、とした。つまり、「2声のカノン。ヴァイオリンは第2のパートを奏し、同度で入る」という意味になる。この場合、第1パートはチェンバロの高音部が演奏する。以下、Ⅲの3~5の各曲もこれにならい、チェンバロは通奏低音プラス2声のうちの1つを受け持ち、他の旋律楽器がもう1声を受け持つのだ、という。
そして、クイケンは「この曲集はすべて楽器編成が記されたトリオ・ソナタと同じ4つの楽器で演奏できるようになっている」(=2台目のヴァイオリンは不要)と考えたのである。
以下に、3つの盤の各曲の楽器編成を表記する。
| リヒター | レオンハルト | クイケン | MAK | |
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.3声のリチェルカーレ | Cemb(ビルグラム) | Cemb(レオンハルト) | Cemb | Cemb |
| Ⅱ.無限カノン | Vn,Vla,Vc | Fl,Vn,Gb,Cemb(コーネン) | Fl,Vn,Gb | Fl,Vn,Gb |
| Ⅲ-1 | 2Vn | Cemb(レオンハルト) | Cemb | 2Vn |
| Ⅲ-2 | 2Vn,Vc | 2Vn,Gb,Cemb(コーネン) | Cemb,Vn | 2Vn,Gb,Cemb |
| Ⅲ-3 | 2Vn,Vla | Fl,Cemb(レオンハルト) | Cemb,Fl | 2Vn,Fl |
| Ⅲ-4 | 2Vn,Vla | 2Vn,Gb | Cemb,Gb | 2Vn,Gb |
| Ⅲ-5 | 2Vn,Vc | Vn,Cemb(レオンハルト) | Cemb,Vn | Cemb,Vn |
| Ⅳ.カノン風フーガ | 2Vn,Vc | Vn,Cemb(レオンハルト) | Cemb,Fl | Fl,Vn,Gb |
| Ⅴ.6声のリチェルカーレ | Cemb(ビルグラム) | Cemb(レオンハルト) | Fl,Vn,Gb,Cemb | Cemb |
| Ⅵ-1.謎の2声カノン | Cemb(ビルグラム) | Cemb(レオンハルト) | Cemb | Cemb |
| Ⅵ-2.謎の4声カノン | 2Cemb(ビルグラム、リヒター) | 2Cemb(レオンハルト、コーネン) | Cemb,Vn,Gb | 2Vn,Cemb |
| Ⅶ.トリオ・ソナタ | Fl,Vn,Vc,Cemb(リヒター) | Fl,Vn,Gb,Cemb(コーネン) | Fl,Vn,Gb,Cemb | Fl,Vn,Gb |
| Ⅷ.無限カノン | Fl,Vn,Vc,Cemb(リヒター) | Fl,Vn,Gb,Cemb(コーネン) | Fl,Vn,Gb,Cemb | Fl,Vn,Gb,Cemb |
なお、幾つか補足説明をしておく。
- 謎のカノンのうち4声のほうは「7小節遅れで2オクターヴ下から入る」が正解。
2声のほうは、B・クイケンの解説では「2小節半遅れで反行で入る」しかない、と書かれている。 -
しかし、レオンハルト盤での服部孝三氏の解説によると「a.3小節遅れ反行」「b.13小節遅れ反行」およびそれらの鏡像a’、b’の4通りあり、レオンハルトは「a」を演奏している、とする。ところが、クイケン盤とレオンハルト盤は同じである。よって、服部氏の解説中「3小節」とあるところを「2小節半」にするのが正しい。
ちなみにリヒター盤でのビルグラムは、上の「a」及び「a’」の2通り(つまり2小節半遅れの正像と鏡像)を録音している。 - 「Ⅴ.6声のリチェルカーレ」は、王に送付された印刷譜では合奏スコア形式に書かれているが、バッハの自筆譜では2段のチェンバロ譜で書かれていて、十分チェンバロで弾ける。それに対し、「Ⅵ-2.4声の謎のカノン」は1台のチェンバロでは弾けない。
-
だが、この配列ではどうしても「4声謎カノン」はチェンバロの音色がふさわしい、と考え2台チェンバロにしたのがフスマンである。フスマンは、カノン・リチェルカーレはチェンバロ、それ以外は合奏で、というコンセプトであり、リヒター盤の他、レオンハルト盤も大筋で同じ解釈である。
これに対して、クイケン盤は全く異なり、とにかくトリオ・ソナタの4つの楽器で全部やる、というコンセプトである。よって、「4声謎カノン」は、2声をチェンバロ、残りを2つの楽器でとなる。またチェンバロ1台で弾ける「6声リチェルカーレ」も、3声をチェンバロ、残りを3つの楽器で、ということになるのである。