モーツァルト「レクイエム」 バイヤー版
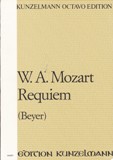
校訂は1971年、ミュンヘン音楽大学ヴィオラ科主任教授のフランツ・バイヤー(Franz Beyer)によって行われた。彼は古楽器奏者でもあり、コレギウム・アウレウムのメンバーとして、当版の初録音にも参加している。
オイレンブルクから、1980年に出版された。その前年にマリナーの旧録音、翌年にアーノンクールの衝撃的録音がなされている。その後も当版の使用が一時流行し、スタンダードになりそうな勢いの時もあった。
のち、出版元はKunzelmannに変わっている。私はこれを入手した。(右写真)
輸入楽譜店「アカデミア・ミュージック」のサイトを見てみると、Kunzelmannから「フランツ・バイヤーによる補筆完成版(2005年改訂版)」というのが出ているようだ。アーノンクールの2003年再録音はこれによっているのだろうか?
この版は、基本的にジュスマイヤー版の骨格はいじらず、ほとんどオーケストレーションのみの修正に留まっているため、抵抗は少ない。判別しやすいジュスマイヤー版との変更点としては
- Rex tremendaeの2拍目の管楽器の合いの手のカット(これはその後の改訂版にも受け継がれている)
- Confutatisの各小節1拍目・3拍目のティンパニとトランペットの打ち込みのカット
(→ランドン版ではこれが2拍目・4拍目に移動している。)
といったところがあげられる。このように、バイヤー版は、伴奏部分のよけいな贅肉をそぎ落とすような改訂が特徴である。
私は他に、Lacrimosaの間奏部分第21小節の、下からずりあがっていくような第1ヴァイオリンの音型をバイヤー版の識別票にしている。(しかしランドン版のこの部分はちょっと聴いただけではジュスマイヤー版との区別がしにくい。)
合唱部分の変更としては、
- Lacrimosa の最後で、ジュスマイヤー版の印象的なテノールの上昇音形(第24小節3拍目から第25小節2拍目)が無く、B→S→Tの順に「Dona eis...」と下降音形で歌い始める。(その前の第23小節のBassから音が変更されている。)
ジュスマイヤー版ではテノールが断末魔の叫び声のようでもあるのに対し、バイヤー版だと各パートが次々とひざまづきながら祈るような印象を受ける。この違いは大きい。 - Osannaのフーガの最後にハ短調ミサK.427のOsannaと同じような終結部を4小節追加する「第2案」を作成している。
最後2小節で1番カッコ「Erster Schluß」(第1終止=従来の形)、2番カッコ「Zweiter Schluß」(第2終止=4小節追加)と表記。
の2点があげられる。
ディスク
- コレギウム・アウレウム盤・・・・1974年、DHM。
- マリナー旧盤・・・・1977年、DECCA。
- アーノンクール盤・・・・1981年、TELDEC。Osanna終結付加無し
- クイケン盤・・・・1986年、ACCENT。Osanna終結付加無し
- バーンスタイン盤・・・・1986年、DG。Rex tremendaeの2拍目でオルガンの強奏を入れる反則技!
- コルボ新録音盤・・・・1992年、Virgin。
- ベルニウス盤・・・・1999年、Carus。
バイヤー自身による解説
コレギウム・アウレウム盤の解説(1975年)から適宜抜粋構成
様式批判的研究は、これらの楽曲(SANCTUS, BENEDICTUSも含めて言っているようである。:山岸注)の声楽部分 − あまりに短すぎる、終結の唐突なOsannaのなさけない展開は別として − が、根本的には何と言ってもモーツァルトにしか由来しえないものであるという見解に達している。
この新版において提唱されている両方のOsannaのための終結部の代案が意図するところは、モーツァルトのミサ曲においてしばしば出会う、終止形を反復して強化するという決まった型を用いることによって、このOsannaの部分をいくらかでもより有機的な形で終わらせることにある。
彼(モーツァルト)の全作品の展望から、モーツァルトが確かにどのようなオーケストレイションは行わなかったかが明確になる。
- Rex Tremendaeにおける、モーツァルト真筆の弦の両外声部間で交わされる峻厳な対話を、3度を用いて「美化」し和らげている
- 「復活した者を皆、既に神の御座の前に呼び出してしまっているのに」(アインシュタイン)、さらに吹奏し続ける独奏トロンボーンの饒舌(モーツァルトはMors stupebitの前までしか続けさせていない)
- モーツァルトがオーケストレイションを仕上げていたOro supplexにおける、理解に苦しむ改竄
といった点が問題である。
モーツァルトの実質を純粋に取り出そうとする努力のためのジュスマイヤーの功績を低く見積もるようなことがあってはならない。彼はその困難な課題を、自分になし得る限り立派に貢献した。
しかしながら、彼の補充の欠陥を、永遠に不可能なものとして我慢しているべきではない。