ムソルグスキー 「展覧会の絵」ピアノ原曲
この曲のカラヤンのLP(旧録音)は、高校の時うちでオーディオ装置を導入して、2枚目に購入したLPであった。高校1年の時のクラスは吹奏楽部員が4分の1を占め、彼らの影響で「惑星」「展覧会の絵」などを聴くようになったのである。
で、この曲の原曲がピアノ曲であることを知り、楽譜を買ってきてプロムナード、古城、ビイドロなどを弾いていた。
モノラル録音
- スヴャトスラフ・リヒテル

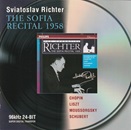
-
PHILIPS。1958年2月25日、ブルガリア、ソフィアでのライヴ・モノラル録音。全30:23、ビイドロ2:14。
(もっとも最初30秒、最後に30秒拍手があるから、正味29分30秒ぐらいである。)
これが西欧レーベルで出たリヒテルの最初のレコードだったという。
とにかく、凄まじい演奏だ。不世出のピアニストもノリにノって踏み外すこともあるわけだ。
当日の他のプログラム(ラフマニノフ、シューベルト、ショパン、リスト)も収録。
2001年に、PHILIPSの50周年で96kHz-24bitリマスタリングされた輸入盤を入手。音に若干奥行きが増した。 - スヴャトスラフ・リヒテル

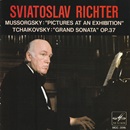
-
メロディア。VICC-2013。1958年8月8日、モスクワでのスタジオ録音。30:26。
完成度の高さという点ではこちらのほうが格段に上である。
56年録音のチャイコフスキー「グランド・ソナタ」(チャイコPC盤収録と同一録音)とカップリング。 - ウラディミール・ホロヴィッツ
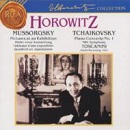
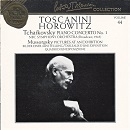
-
RCA。1951年4月23日、カーネギーホール、ライヴ録音。
全29:25、ビイドロ2:35。
トスカニーニとのチャイコフスキーの協奏曲(左1941年盤、右1943年盤)とカップリング。
なお、1947年のスタジオ録音もあるらしい。
原典通りではなく「ホロヴィッツ版」と明記されている。初っぱなのプロムナードから所々オクターヴ上げたり、ビイドロはアルペジォでかつボツボツ音を切ったりなど、とにかくいろいろやっている。キエフの大門の最後など細かい音符の連打で技巧をひけらかしている。
ステレオ録音
- バイロン・ジャニス
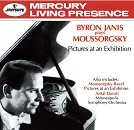
-
MERCURY LIVING PRESENCE。1961年9月、ニューヨークでの録音。
ピアノの音色がこの時代のものとは思えないほど鮮明である。終曲などでちょっと楽譜をアレンジして弾いているようにも聞こえる。ドラティ指揮ミネアポリス交響楽団のラヴェル編曲版の録音(1959年)とカップリング。
ジャニスは1928年、東欧系ユダヤ人の両親のもとにペンシルヴェニア生まれ(本来の姓はヤンキレヴィッチYankilevich)。少年時代からジュリアード音楽院に学び、コルトーやラフマニノフから影響を受けた。15歳でトスカニーニ指揮NBC交響楽団と共演。その後、これまた少年時代のロリン・マゼールの指揮でラフマニノフの協奏曲を演奏した。これをホロヴィッツが聴いていて、その招きで4年間彼に師事した。ボストン響・フィラデルフィア管とも共演し、1948年にカーネギー・ホールでリサイタル・デビュー。1951年にはヨーロッパツアーを行った。1960年にはソ連に派遣されて、(これより前にクライバーンのチャイコフスキー・コンクール優勝はあったが)彼の演奏は“雪解け”時代の米ソ交流の幕開けとなった。当ディスクには、1962年にモスクワで録音されたショパン「練習曲第15番」「ワルツ第3番華麗なる円舞曲」の2曲も収録されている。 - カティア・ブニアティシヴィリ

-
SONY。2015年8月23-26日、ベルリン、フンクハウス・ナレーパシュトラーセ、ザール1での録音。
カップリングはストラヴィンスキー「ペトルーシカ」からの3楽章、およびラヴェル「ラ・ヴァルス」。
アルバムタイトルは「Kaleidoscope」(万華鏡)。グルジア(ジョージア)生まれの女流ピアニストによる豊かな音色が聴けるアルバムということか。録音場所は、旧東ドイツ放送局ホール→スコアリング・ステージ→「フンクハウス・ケーペニック」と改称されてきた、バレンボイムやヤルヴィのベートーヴェン交響曲全集も録音されたところである。
mercariで売却した。 - ウラディミール・アシュケナージ
-
DECCA。1982年録音。全32:15、ビイドロ2:30。
上の2大巨匠以外の録音がなかった時に現れたデジタル録音。
アシュケナージ自身がオーケストラ編曲・指揮した録音もある。 - アナトール・ウゴルスキ

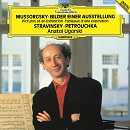
-
DG。1991年録音。全36:17、ビイドロ2:23。
カップリングはストラヴィンスキー「ペトルーシカ」からの3楽章。
ベートーヴェンの「ディアベッリ変奏曲」と並んで彼のデビュー録音となったものである。「ビイドロ」でややテンポかせ前のめりになってライヴっぽい盛り上がりを見せる。
この曲は、ラヴェル版だとゆったりとした感じで演奏されるのが普通だが(それでも2:40〜2:50ぐらい)、ピアノの場合オーケストラよりも音が保持されないため、アシュケナージの弾く2:30ぐらいが標準である。どちらにしてもインテンポで演奏されることには変わりがない。それはビイドロを「ポーランドの牛車」として解釈しているから、そうなるのである。
しかし、この曲にはもっと奥深いものが潜んでいる。自分で弾いてみるとわかる。どうしても前のめりにならざるを得ない感情がわき上がってくるはずなのだ。「ビイドロ」はポーランド語では家畜や獣を意味する言葉であり、ロシアでは「しいたげられた人々=農奴」の意味もあるのだ。
テンポが前のめりといっても、アシュケナージとは7秒しか違わない。しかし、この7秒が表現しているものは大変大きい。 - イーヴォ・ポゴレリチ

-
DG。1995年録音。全42:16、ビイドロ4:19。これは遅い。
全体としてちょっと思わせぶりなところの多い演奏だ。4D録音でピアノの音が相当リアルに録られている。
ラヴェル「高雅で感傷的なワルツ」とカップリング。 - 松田華音
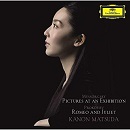
-
DG。2017年2月、軽井沢、大賀ホールでの録音。
カップリングはプロコフィエフ「ロメオとジュリエット」から10の小品である。
彼女のデビュー2枚目の録音。