J・S・バッハ 平均律クラヴィア曲集
第1巻は、90ページにわたる自筆楽譜帳が残っている。「平均律クラヴィア曲集、あるいは、全ての全音と半音を長3度つまりドレミに関しても、短3度つまりレミファに関しても用いて作られたプレリュードとフーガ。音楽の学習を志す若い人々の有益な使用のため、さらには、すでにこの学習に熟達した人々の特別な慰みのために、アンハルト=ケーテン公殿下の楽長であり、その室内楽団の監督であるヨハン・セバスティアン・バッハがこれを起草し完成す。1722年」という装飾文字の表題がついている。
しかしこの第1巻の曲集の中のいくつかは、1720年に書き始めたと明記された「長男ヴィルヘルム・フリーデマンのためのクラヴィア小曲集」という楽譜帳の中に見られる。(この楽譜帳には「インヴェンションとシンフォニア」も入っている。)
グノーの「アヴェ・マリア」の伴奏部分として有名な第1番から始まり、「平均律」の中の最高傑作第8番変ホ長調、そして終曲はこの全曲の締めであることを明らかに意識した大曲第24番ロ短調(プレリュードは反復記号で前半後半にわかれている)である。
第2巻は、ロンドン大英博物館に所蔵された通称「ロンドン自筆譜」がある。しかしこれは1冊の楽譜帳ではなく、1曲ずつ1枚の楽譜用紙に記されている。その用紙は2つ折り4ページで、内側にプレリュードが、そして全体を裏返して演奏できるように外側は4ページから1ページにかけての形でフーガが書かれている。というわけで1枚ずつバラであるためか、「ロンドン自筆譜」は第4・第5および第12曲が欠落した21曲しかない。
このようにバッハ自身の手で「第2巻」としてまとめられたわけではないこの曲集は、作曲年代も第1巻とほぼ同じ頃、あるいはそれ以前の曲もあれば、1735〜45年頃の様式のものもある。
モノラル録音
- エトヴィン・フィッシャー

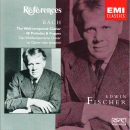
-
EMI。第1巻が1933〜34年録音。第2巻が1935〜36年録音。
フルトヴェングラーの第9、カザルスの無伴奏チェロ組曲と並ぶ、別格・伝説的録音。
結構テンポが速く − 3枚組だ − 古くささなど微塵も感じさせない。
1999年末、バッハ没後250年を前にART処理された輸入盤がリリースされたので買い直した。
ステレオ録音
- グレン・グールド

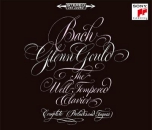
-
ソニー。
第1巻が1962〜65年、第2巻が1966〜71年にかけて、1曲ごとに別々に録音している。
スラーでないところは音を丸く短く切ってメリハリをつけており、それがチェンバロ演奏と通ずる演奏様式になっている。
レーザーディスクになっているTV番組で、グールドは、この平均律は、「フーガは素晴らしいが、そのフーガとプレリュードの組み合わせが、全くてんでんバラバラだ」というようなことを語っている。
SBMリマスターの輸入盤の第1巻・第2巻分売を持っていたが、2016年1月、2012年発売のSACD Hybrid国内盤(グールド生誕80年、没後30年記念)を入手(写真)。分売輸入盤は手放した。
- スヴャトスラフ・リヒテル

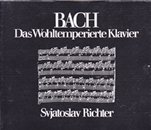
-
メロディア(ビクター)。1970,72,73年録音。
吉田秀和氏が「一生持っていて繰り返し聴くに値する演奏」(朝日新聞1974年12月19日「音楽展望」)と絶賛している。
遅めのテンポで丁寧に弾いており、ある意味でこの曲集の最もロマン的な演奏と言えよう。第1巻の第8番は10分以上、終曲はリピートを実行して15分以上もかけている。残響の多い録音。2012年にSACD Hybrid国内盤が出たので買い直し、従来盤は手放した。
DSDマスタリングは杉本一家氏がつとめている。録音場所データもきちんと表示されている。
それによると、第1巻は1970年7月21日〜31日、ザルツブルク、クレスハイム宮およびエリーザベト教会。第2巻は、1972年8月29日〜9月6日、クレスハイム宮、および1973年2月24日〜3月8日、ウィーン、ポリヒムニア・スタジオ。 - フリードリヒ・グルダ
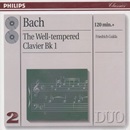
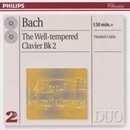
-
PHILIPS。廉価輸入盤2枚組×2セット。
1972年4月(第1巻)、1973年5月(第2巻)、VillingenのMPS-Tonstudioでの録音。
音楽的にも、録音としてもグールドとリヒテルの中間をいくものである。
オリジナル楽器の録音
- グスタフ・レオンハルト

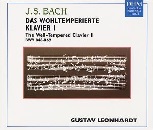
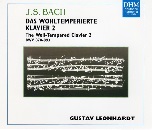
-
DHM。第1巻が1972〜73年録音。第2巻が1967年録音。於キルヒハイム、フッガー城、糸杉の間。
使用楽器は、第1巻がパスカル・タスカンをモデルにしたデイヴィッド・ルビオによる1972年製コピー、第2巻がJ.D.ドゥルケン(1745年アントワープ製)をモデルにした、ブレーメンのマルティン・スコヴロネクによる1962年製コピーである。
しみじみと感動できる。キー操作で鳴らす弦の数を減らしリュートのような音で演奏している曲もある。 - スコット・ロス
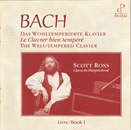
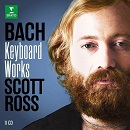
-
ディスク・ペレアス。1980年、カナダ放送によるスタジオ録音。
コープマンのと違って相当「真面目な」演奏である。遊び心がないわけではないが、テンポとリズムがきちんとしている。
第1巻のみを輸入盤2枚組(左)で入手。その後入手したERATOの11枚組BOX(右)で第1巻・第2巻全曲を揃えた。
ディスク・ペレアス盤は売却することにした。 - トン・コープマン
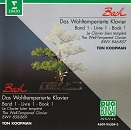
-
ERATO。1982年録音。第1巻のみ所有。
一度コープマンを生で見てしまうと、何の録音を聴いても、あの楽しそうなコープマンの様子が頭に浮かんできてしまう。この録音でもそうである。